←とうらぶ目次へ戻る
Twitterとネタ違いで開催した鶴さにアドベントカレンダーネタのログです。
はじまりのクリスマス 1
はじまりのクリスマス 2

選抜隊は、今日の夜中までには帰る予定だ。
いつもならとっくに開いているはずの箱が、今夜はまだ開かないのが不安で、布団に入ってからも枕元に置き、何度となく指先で転がしては開けようと試みる。
なにかの時に寝不足では使い物にならないからと、お風呂の後は自室に押し込められるように連れて来られ、切国に寝るようにと厳命されてしまった。
いつ帰ってもいいように、お風呂も食事の仕度も万端で。
常の夜番とは別に転送装置の前にも一振置こうと決まるや、名乗り出たのは一期だった。
選抜隊には乱や厚、前田も加わっている。一期も今、私と同じように気を揉んでいるに違いない。
「切国、いるんでしょ?」
「……ああ」
声を掛けると、いらえはすぐに返った。
「廊下、寒いでしょ。こっちにくれば?」
「馬鹿を言うな。女の寝所に入れるか」
「いつも起こしにくるくせに」
「それとこれとは話しは別だ」
「そうかなぁ。ね、一期もずっとあそこじゃ寒いでしょ。何か温かい飲み物でも持って行ってあげてくれないかな」
「……わかった。あんたは寝るんだぞ」
「はあい」
眠れるはず、ないんだけどな。
「覚悟はしておいたほうがいい」
選抜隊が帰らぬままに夜が明けて、そうして再び夜が来た。
部隊からの連絡は一度もなく、ならば政府からは何か来るのではと端末の前に張り付いていたものの梨のつぶてだ。
昼もろくに食べなかった私は、とうとう初期刀に広間へと強制連行されてしまった。
いつもの場所に座って隣が空いてしまうことを気遣われたのだろう。一期の隣に座るように促すと、切国はその反対隣へと腰を下ろした。
膳におかれたほうとうからは湯気が昇り、味噌の香りが食欲をそそる。かぼちゃがたっぷり入っていたそれを見下ろしながら、そうか冬至かと思い至った。
「冬至……」
「そうですな。さっき薬研が風呂に柚子を入れたと言っていました」
琥珀の瞳を細めて微笑んだ。そんな表情を浮かべるのが、信じられない気がした。
だって帰って来ない中には一期の弟たちだっているのに。
そうして軽く広間を見渡せば、いつもより少し静かな以外は常と変わらない食事の風景だった。
私を見つめる琥珀が切なげな苦笑にかわり、なんで、と喉から出かかった言葉を飲み込んで息を詰める。
冷たいわけではない。
心配していないはずがない。
けれど、戦だ。帰って来ない可能性がある。そういうものの直中に居る。それだけだ。
少しも納得のいっていないことを無理矢理心の中に押し込めて箸を取りながら、「ごめん、一期」と呟く。
小さな小さなその声を拾い上げた長兄の刀は「主に謝られるようなことはなにも……むしろ、せっかく選んで頂いたのに、功を立てることが適わず終わるならば、それを詫びなくてはいけませんな」などと言いながら、私に遅れてほうとうを口にした。
選んだのは鶴丸だ、と。だから謝られるようなことはひとつもないのだと言いかけて、やめた。
その言葉はどこか責任転嫁のように思えたからだ。
責任。
そうだ。今回の選抜隊を選んだのが私だったら、帰ってこない不安だけでなく、もっともっと申し訳ない気持ちになったかもしれない。それを鶴丸が引き受けたのだとしたら。
咄嗟に立ち上がりかけると、短く「食ってからにしろ」と告げた切国はほうとうを口にする。
「でも」
「寝ない、食わないではどうにもならない。ここであんたが倒れでもしてみろ。目も当てられないだろう」
そう言われてしまえば、従うしかない。
「切国。鶴丸は、こうなるかもしれないってこと、知っていたね?」
確認をこめて尋ねれば「ああ」と短く答えが返った。
部屋に帰って、政府から送られた命令を何度となく読み返す。
『たぶんこれでお上の意向に添った働きが出来ると思うぜ?』
鶴丸は、この文章の中から何を読み取ってあんな風に言ったんだろう。
短刀中心の編成。
夜戦と見たのか。狭い場所での戦いを強いられると見たのか。
でも、ここにはそんな情報はひとつもありはしない。
何もわからない手つかずの地域だから、慎重にことにあたれという内容のことが書かれてあるだけだ。
「覚悟はしておいたほうがいい」
食事の後、すぐに部屋にやってきた切国は、被った布をはずし、まっすぐな視線でそれを告げた。
「正直──あいつらの帰還は厳しいと思う」
薄々感じていたことをつきつけられて、足もとにぽっかりと穴が空いて落ちていくような錯覚に陥る。
「や、でもまだ……政府から、そう政府からも何も連絡が来てないよ」
声が、震えた。認めるのが怖くて、違うと言って欲しいと乞うように見つめると、何かを言いかけた唇は躊躇うように引き結ばれた。
ふと、外が騒がしくなった。
転送装置の起動する音が響く。ばたばたと外に駆け出す者たちの足音に釣られて立ち上がりかけると、「すぐに駆け出そうとするなっ。敵襲だったらどうする」と強く窘められた。
(*12/23が抜けているのは間違いではありません。23日分が12/24です)
あの日、転送装置の起動音に皆が集まる中、帰って来たのは乱だった。
切り裂かれた服は真っ赤に染まり、倒れ込むように帰還した。
「急げ!」
「手入れ部屋へ!」
そんな声が飛び交う中、再び起動した門からは今度は今剣が現れた。
虚ろな目に生気はなく、よくぞ戻れたというほどに血にまみれてボロボロだった。
帰還した二振の処置を済ませた頃、手入れ部屋に前田と加州が担ぎ込まれた。
普段、戦からの帰還は部隊全員が揃って帰還する。それは無事に成果をあげてきた時でも、負傷者を出しての場合でもそう時間を空けることなく六振が帰ってくる。こんなに時間に差をつけ、しかも戻る誰もがここまでの傷を負ってくるなど初めてのことだ。
札を使うとはいえ、立て続けに霊力を使うのはしんどいものの、そうも言っていられない。
お臍の下にぐっと力を込めて集中し、札に霊力を込めていく。
「主っ」
一期に抱えられて担ぎ込まれたのは厚だった。腿に走る刀傷は骨にも達してそうな勢いだ。肩の傷も抉れていて、刀を手にすることすらできそうにないほどだ。小さく呻きながら浅い息を繰り返すのを前にして、新たな札に手を伸ばす。
と、その時。強く手首を掴まれた。厚の血まみれの手が、訴えるように痛いほど私を掴まえている。
「厚、離して。手入れが出来ないでしょっ」
流れ出る血に、早くあれをどうにかしなくては気が急く。その心のままに声を荒げると、「すまねえ、大将」と掠れた声が耳を打った。泣きそうに歪んだ表情に視線をやると、「すまねえ、……丸さん、が俺を、俺たちを、逃がして……」と振り絞るように言いながらこちらを見ていた。
ドクンドクンと心臓の音が全身に響き、冷たい汗が背を滑る気がした。喉に何かがつかえたような、熱のない指先が首に回され緩く締め上げられているような錯覚に陥りながらも、駄目だと言い聞かせた。今はこの目の前の刀の痛みを一刻も早く取り除かなければいけない。
「後で、ね。先に手入れをさせて。お願いだから」
瞳を覗きこむと、物言いたげにこちらを見ていた彼は口を開きかけ、唐突に手首が解放された。気を失ってしまったらしい。
すかさず札を手にし、手入れを開始した。
鶴丸は、帰ってこなかった。
撤退を決めた時、厚は鶴丸と共に殿を務めたのだという。最初の四振を逃がすだけの時間を稼いだ後、彼等も転送装置を目指して走った。走ったと言っても、もうその頃にはかなりの深手を負っていたらしい。
そうして、新手が現れた。
幾ら問い合わせても一向に返事をくれなかった政府からは、あの時代に残っている刀剣男士の反応は全く検知できないという返答があった。
つまりはそういうことだろう。
選ばれた15の本丸。そのうち、10カ所の本丸の部隊は全滅だったそうだ。
5振も帰還したのはうちともう1カ所、上位ランクの本丸だけだったらしい。
しかも、うちの本丸は鶴丸の采配のお陰で、戦闘状態に陥る以前に地理的に見て転送先にするのに適していそうな場所の調査、同じく敵がそこを起点に時空を跳躍しそうだという場所、出くわした敵の構成や強さなど各自が分担していた情報を多く持ち帰っていたことで、政府からは随分と労われ、また褒賞も与えられた。
馬鹿な私でもわかった。政府が欲しかったのは、新しい戦地に実際に派遣した刀剣男士が見聞きした情報だった。
この件で政府に呼ばれて集まった審神者は一様に年若かった。折れた男士は残念だったねと口先だけで労られ、堪りかねたひとりが「捨て石に扱いされるいわれはない」と噛みつくと、「また顕現すればいいじゃないか。なにしろきみたちは若いんだから」などと諭され、こいつらには何を言っても無駄なのだろうという徒労感を共有出来たに過ぎなかった。
文机に置かれた4つの箱。
彼が遺したこれが開かないことこそ、彼がどこかで生きている証なんじゃないかと。しばらく経ってから、切国に言ってみたことがある。
折れて神力がなくなったなら、この箱は開くのが普通なんじゃないか、と。
翡翠色の瞳に労るような色を浮かべながら、それでも「それはない」と初期刀はきっぱりと断言した。
「考えてもみろ。俺たちは分霊だ。分霊一振が折れた所で大元が損なわれたわけじゃない。それだけのことだ」
突き放すようなもの言いは、無駄に期待を抱かないで済むようにする為の彼なりの優しさだとわかるから、それを最後にもう二度と、私は無駄な希望を口にすることはやめた。
『たいがい嫌いにならないか』
最後になってしまったカードの意味を、その後幾度も考えてみた。
恋愛対象にはなりえなかった私と、普通に主従としてうまくやっていきたいと思われていたかもしれない。
もしかしたら、主としてならほんの少しくらいは好かれていたかもしれない。
かもしれないばかりが並ぶ仮説も、その後この本丸には二度と鶴丸国永が顕現しなかったという事実、それがすべての答えに思えた。
この箱の中には何が入っているのだろうと今でも時々考える。
その時、彼が何を思ってくれていたかはともかくとしても、これらは私がどうしようもなく愚かだったことを知らしめるものなのは確かだ。
開けることの出来ない4つの箱は、私が審神者としてこの本丸にある間、ずっと執務室の机の上に飾り続けた。

(Twitter版の 12/21の夜にあたります)
この支社への出張の時には必ず立ち寄る創作割烹の店がある。海が近いこの地ならではの魚介類を堪能できるその店は、オーナーだという男と気が合って、行く時には連絡をいれ飲み交わす仲でもあった。
年に数回会うかどうかというその男と呑むのは居心地がよく、不思議と愉しい酒になると思っていたものだが、それもそのはず、前世の全てを思い出してみれば昔なじみの刀剣だった。
「え?思い出したの!?」
「ああ、だから他人行儀に五条さんってのはやめてくれていいぜ、光坊」
まあどちらでも構わないんだが、と言いながら、スマホを構えて利き酒セットを撮る。ここに彼女が居たら、嬉々としてブラインドでの当てっこに挑戦するくらいはしただろうか。
送信すれば既読はつくが、やはり返信される気配はない。昨日からずっとこんな調子で、だからこそ、やはり彼女は『主』で、しかも記憶もあるであろうことを半ば確信した。
前世のことを思い出したのは、ほんの一ヶ月前のことだった。
映画や小説では、命の危機に瀕してだとか前世と同じ出来事を前にして、それをきっかけに記憶を取り戻すなんてものを目にしたことはあるが、いざ自身の身の上に起こってみれば朝スマホのアラームを止めた時にはもうすべてを思い出していた。
彼女と初めて会ったのは残業帰り、会社のエレベーターで一緒になった時のことだった。もう社内には誰も残っていなさそうな夜間、エレベーターにも誰も乗っていないのだろうと思っていたのだろう。疲れた顔をした彼女は俺が乗っているのに気が付くと、スカートが捲り上がりそうなほどに飛び退いて見せた。
あまりの勢いに何事かと思えば、お化けと間違えたなどと子どものようなことを言うのがなお可笑しくて。腹の虫を鳴かせた彼女を食事に誘えば、即答で断られたのに面食らった。
自慢じゃないがモテる。無駄にモテる。黙っていても女は寄ってくるから、鬱陶しい思いをしたことはあれど、不自由したことはない。
だから、やたらと誘って誤解をされるのも面倒だとそう滅多に女を誘うなんてことはしないようにしていたはずが、彼女とはもう少し話してみたい気もした。
それをあっさり断られたものだから、つい食い下がってしまったが、思い返してみればあんなことをしたのは彼女が初めてだった。
『きみの好きなものをご馳走するぜ』
そう言って承諾を貰い、店の選択を彼女に任せて歩くと、連れて行かれたのは駅前のお世辞にも綺麗とは言えないらーめん屋で、また驚いた。男同士ならいざ知らず、男が奢ってくれるという時にそんな店を選ぶ彼女をますます面白いと思った。
いざ食事を共にしてみれば、餃子でもらーめんでもぱくぱくと気持ちいいほどよく食べる彼女の箸運びが随分と綺麗で、そういえば好意らしい好意を向けたのはあれが最初だったかもしれない。
恋愛感情を抜きにした関係だからこその気安さや愉しさが、一定以上は近づくことの出来ない物足りなさに変わっていくのに、そう時間はかからなかった。
それとなく誘いかけても、彼女にとって俺はどこまでも飲み友達のようで、靡くどころかそれが誘い文句だとすら気付かれない。
そろそろ勝負をかけるかと思っていた11月。すべてを思い出した。
『だって、クリスマスだよ?』
『異教徒の神の生誕がそれほどめでたいことか?』
『悪いけどそっちはついでかな。街中きらきらで、もうそれだけで楽しくて』
ツリーを飾りながら笑う記憶の中の可愛い雛は、クリスマスを心待ちにして本丸中をはしゃぎまわるように飾り付けていた。
だから。
彼女がクリスマスは嫌いだとなんの感情も浮かべない表情で言ったのには驚いた。
出会う前に手酷い目にでもあったのか。
それとも──。
いつかのクリスマスを台無しにしたことは自覚していた。
だから、きみのクリスマスをもう一度、きらきらしてそれだけで楽しいってものに塗り替えたいと思ったんだ。
「ふうん、アドベントカレンダーか。懐かしいね。……主にとってあんまりいい思い出じゃないと思うけど」
「だろうな。だから選んだのさ」
燗酒で満たした猪口に口をつけた伊達男は、咎めるような視線を寄こしながらエイヒレをつまみ上げる。
「僕たちもやりたいって言ったのに。今年は自分だけでやるから駄目だって譲らなかったクセに、最後までやり遂げないなんて、ホント、格好悪かったよ」
「はは、すまんすまん」
無邪気な雛鳥は、好きだ好きだと囀っては後をついてきた。可愛らしいばかりの人の子を、愛おしいと思うようになったのはいつのことだったか。
彼女が俺に向けるそれはひどく綺麗で、己の抱える欲とはどうにも違うように思えた。だから、儚く純粋なそれに手を伸ばしたら、壊してしまうんじゃないかと躊躇した。
彼女の憧れを壊したくないと思いながら、それでもクリスマスには手に入れようと心に決めて。
雑誌をめくり、一度やってみたいんだよねぇなどと呟いていたアドベントカレンダーに便乗した。
結果。
彼女の大好きなクリスマスを酷い思い出で穢してしまった。
「鶴さん、あの後ね。僕らの本丸は三年で閉じたんだ」
「へえ……」
小振りの小さなグラスに注がれた酒を口に含む。すっきりと爽やかな風味のこれは、あの子が好きそうな酒だ。
「三年、か。早かったな。嫁いだのか」
「本当にわかってないね、鶴さん。まあ、わかってなかったのは僕らも一緒だったけど」
「なんだそりゃ」
もったいぶった言い回しに、ちらと視線を投げてる。
運ばれてきた海老しんじょを揚げたものに箸をいれれば、からりとした衣の中はふんわりとして旨そうだ。
「あの後、主はどうなったと思う?」
「どうもこうも、三年で審神者を降りたんだろう?」
本丸を閉じたということは恐らくそういうことだろう。
折れて戻ることが出来なくても、彼女はきっと大丈夫だろうと思っていた。人はどれほど悲しいことがあっても、時間と共にそれが和らぎ、再び歩き出す生き物だ。
だから、幼い恋を突然取り上げられた彼女も、いつかまた誰かを恋い慕うようになるのだろうと思っていた。
その為にも、俺の想いはもう一欠片も彼女には明かさないと決め、残りのアドベントの箱は開かないように咒をかけたのだから。
出陣の間際。あの日のカードのメッセージに不服を訴えていた彼女が『庭のイルミネーション。クリスマスが終わって片付けちゃうまでに、一度散歩に付き合ってよ』と袖を引いた。
それすらも、煙に巻いて、約束はしなかった。叶えられない約束ほど残酷なものはないと思ったからだ。
行きたくない、とは思わなかった。戻れないだろうと感じながらも、主たる彼女に一番刀だからと誇らしそうに言われ、拝命した役目を果たせることが嬉しかった。
願わくば、彼女の元に戻りたいと思ったのもまた本当だけれど。
三年後。
いったいどんな男が彼女の心を癒し、攫ったのか。
考えるのも悔しくて、もうひとつのグラスは味わうのも忘れてひと息に空けてしまう。
「あの後……あの本丸は翌年からずっと上位ランクに入り続けてたよ」
「へえ、凄いじゃないか。あの主がねぇ」
「鶴さんも僕らも、主の想いをみくびってたよ。頼りない雛のようなあの子が、懐くように、憧れるように、好きだと繰り返して、そうしてそれを恋だと呼んでいるんだと思ってた」
「……」
「でも違う。違ったんだ。主は鶴さんに負けないくらい、鶴さんのことを本当に想ってた」
彼女の嘆きの深さを知らしめるように代弁する光忠は遠い目をしている。その視線の先には、泣いて悲しむ彼女の姿が浮かんでいるんだろうか。
「泣かすつもりはなかった」
「主は泣かなかったよ。一度も泣かなかった。鶴さん以外のみんながひどい有様で戻った時も、鶴さんが、もう戻っては来ないだろうって諦めた時も」
「……は?」
そんな薄情なことがあるものか、と真っ先に思った。泣いて泣いて泣き尽くして。そのくらいはするだろうと思っていたのに、泣きもしなかったんだろうか。
けれど、光忠の語る彼女のその後に、自分の思い違いを突きつけられる羽目となった。
あの任務の後。
変な気を起こさないかと心配した皆は、夜間も含めた四六時中誰かしらが彼女の傍にいたそうだ。
そんな心配を他所に、生還した5振の持ち帰った情報を丹念にまとめ上げて政府に報告し、彼女は褒賞を得たのだという。
それを封切りに、主は恐ろしく精力的に業務に励んだ。サボることもせず、息抜きと称して出掛けることもせず、ただただ審神者としてのそれを優先し続けた。
翌年からは常に上位のランクに入り続けたという。
「泣かなかったけどね、その代わり、あれ以来一度も笑うこともなかった」
楽しげにはしゃいで、窘められては口を尖らせて。年の割には幼げに見えたあの主を思い起こせば、いつだって笑っていた。
そんなあの子が、一度も?
「上位本丸として表彰されても、ちっとも嬉しそうじゃなくてね。逆に、そうしてこなかったこれまでの自分を責めてるみたいだった」
「お花見も、西瓜割りも、ハロウィンも……何をどう計画しても、主は来なかった。ずっと閉じこもって働き続けて、三年で──死んでしまったよ」
スマホを取り出す。
相変わらず彼女からの返信はひとつもない。
彼女は本当に前世を覚えているんだろうか。
思い出しているなら、それならどんな思いで『俺』の傍にいたのか。
衝動的に電話を掛けても、彼女はやはり出てはくれない。
『クリスマスは、嫌い』
俺の驕りでなく、きみは俺が好きだろう?
『だって五条は友達なんだもの』
友達という呼び名で牽制していたわけじゃない。
きみは、きみ自身にそう言い聞かせていたんじゃないのか?
『五条、クニナガさん』
酔っていようと、間違っても鶴丸とは呼ぶことはなかった。
裏を返せば、そこまで頑なに抑え込んで隠している痛みが、今でもあるってことじゃないのか。
「どうしたの、鶴さん」
「しくじった……あぁっくそっ!俺の中では、今夜には全部片付けて帰るつもりでいたのに!」
今回の出張は元々金曜日までの予定だった。
それでもどうにか木曜にはケリをつけて、金曜日の退社時にはそのままあの子を拉致するつもりでいたのに。
それを、最後の最後であの狸腹の社長が、契約は明日の方が日がいいからなどと言いだしたお陰で、予定通りに明日の昼迄は拘束されることになってしまった。
何度か電話を掛けてはみても、やはり出ては貰えない。
メッセージが既読にもならないあたり、寝たのか、スマホを放り出しているのか。
光忠の笑う気配に、苛々とスマホを眺めていた視線を上げる。
「あの頃は、主ばかりが鶴さんを追いかけていたように見えてたけど、そうでもなかったよね。鶴さんは鶴さんで、主が追ってきているかと、いつもちらちらと背後を見ていたような気がする」
「まあ……否定はしないな」
「次は主を連れてきてよ」
「袖にされなければな」
「されるつもりないくせに」
「どうだか。まあ……健闘を祈っててくれ」
合わせたグラスが軽い音をたてた。
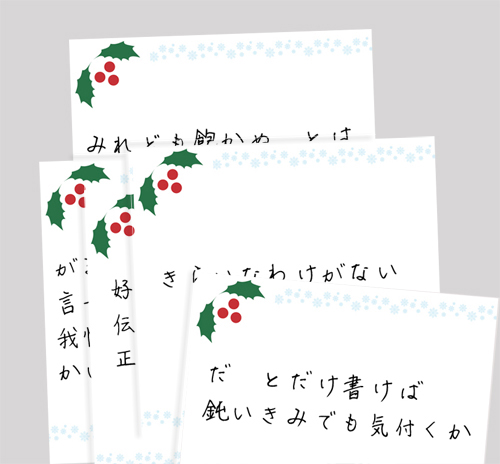
←とうらぶ目次へ戻る