←とうらぶ目次へ戻る
Twitterとネタ違いで開催した鶴さにアドベントカレンダーネタのログです。
「きみは朝が弱いっていうよりも、単に夜更かしが過ぎるんじゃないか」
「ほら、眠れないほど鶴丸を想ってるんだよ。恋煩いってことで」
「戯れ言はいいから、早く仕度してくれ」
「鶴丸が今日も冷たい…でも好きだよ」
のろのろと布団から身を起こしてそう言えば、金色の目を眇めた彼は呆れたようにため息をひとつ。
「みんな待ってるぜ」
こんな風に告白をスルーされるのもいつものことだ。
鶴丸を顕現して1年。好きだと気付いて半年。毎日毎日好きだと伝えても、彼にはてんで相手にして貰えない。
もっとも、千の齢を数える神サマが二十歳そこそこの、霊力だけが取り柄の私なんかを相手にしないなんてことはわかっているんだ。それでも溢れてきてしまうものは仕方ない。
ふと、小引き出しの上に積まれた小箱の山が目に止まった。昨夜寝る前にはなかったものだ。
箱にはカラフルな色でひとつひとつに数字がふってある。
24番が最後になっているそれは、アドベントカレンダーのようだった。

「鶴丸」
障子をひいた白い背中に呼び掛ける。
肩越しに振り返った彼は、私の視線の先に気付いたのか「あぁ、やってみたかったんだろう?」
アドベントカレンダーをやってみたい、と話したのは先週鶴丸とおやつを食べている時だったか。
クリスマスパーティやプレゼントの準備について話している合間に、そういえばと口にした。
12月1日からイブまでの毎日、ひとつひとつ開けては飴やチョコレートを手にしていくのはワクワクして楽しそうだと話せば、きみはすぐに全部開けて中を確かめたくなるんじゃないかと笑われた。
積まれた箱はクラフト紙に包まれ、いかにも手作りという風情だ。やってみたいと言った私の為に作ってくれたのだろう。
「ありがとう! 大好き!」
「喜んで貰えたなら何よりだがな。早く身支度してくれないか」
「はーい」
そっけなく部屋を出て行った背中を見送って、早速『1』の小箱を開けてみた。
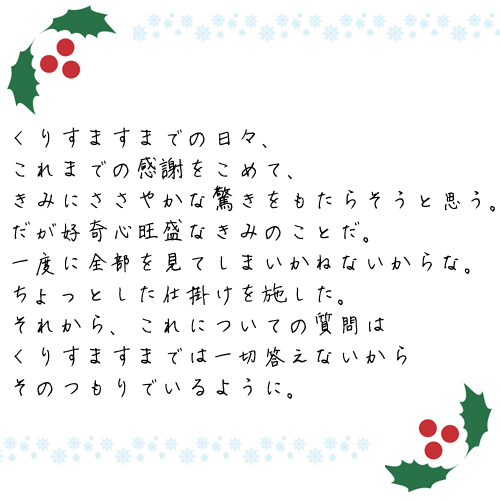

──これから毎日楽しそうだ。
「あるじさん、それ何?」
そろそろ夕方になろうというのに一向に終わらない書類にうんざりしてぱたりと机に伏せると、後ろに控えて待っていた乱が手元を覗きこんで小首を傾げた。
「ふふふ~聞きたい?」
書類の上に転がすように弄ぶそれは、昨日鶴丸がくれたアドベントカレンダー。2が印されている今日の分の箱だ。
今日の分なのになぜか開かないこの箱に、昨夜から何度となく挑戦してみるものの、たかだがクラフト紙で包んだだけのそれがなぜだか紙を剥ぎ取ることすら出来ない。
気になって朝から執務室に持ち込んではみたものの、未だ開く気配はなかった。
これに関する質問には一切答えないと昨日のカードで宣言されている以上、尋ねてみたところで教えては貰えないだろうと朝餉の席でも何も訊いてみなかったけれど、こんなことならヒントくらいは貰えばよかったかもしれない。
「鶴丸さんがくれたんでしょ?」
「え?なんで知ってるの?」
答えながら思わずにやにやしてしまうのは仕方ない。だってこれまで少しも、これっぽっちも、全く、相手にしてくれなかったあの鶴丸が、私の為に作ってくれた特別なアドベントカレンダーだ。
なんなら、この一方的な片想いを生温かく見守ってくれている本丸のみんなひとりひとりに自慢してまわりたいくらいだ。
「そりゃ……まあわかるよ。だってあるじさんが嬉しそうだからさ」
「そうなの。あのね、これは鶴丸の!私への!愛の結晶!!」
「こら、勝手に脚色するな」
ふいに声が響いた。開かれた障子から覗く金色は、不機嫌そうに眇められている。
「あ、鶴丸、おかえり……ってあれ? 早くない?」
「そうか? 報告をと思ったが、きみはまだ終わってないようだな」
「うぅ、もうちょっとで終わるもん」
「ならとっとと終わらせるんだな。先に風呂にでも入ってくる」
「あ、鶴丸さん」
出て行きかけた鶴丸を呼び止めたのは乱だった。
「これなに?」
「主に聞かなかったのか?あどべんとかれんだーというやつだ」
「あど、べんと……ああ、クリスマスまで毎日ひとつずつ開けていくあれかあ」
「ま、子どもの遊びだな」
「むぅ、ひどい」
「遊びの割に随分神力込めてあるね」
乱の言葉に乗っかるように、私も急いで声を上げた。
「そうだよ、鶴丸。これ今日のぶん開かないんだけど」
どんな神サマパワーだか知らないけれど、開かなかったらちっともアドベントじゃない。唇を尖らせて尋ねると、彼はニヤリと口の端を引き上げた。
「開かないように仕掛けがしてあるからな。そうでないと、きみ、一度に全部開けるか、毎日日付が変わって開けられるようになるまで寝ないで待ち構えるだろ?」
う、ばれてる。
昨夜日付が変わると共にもの凄く頑張って、勢い余って柱に頭をぶつけ、夜警当番が何事かと慌てて駆けつけてきたのも鶴丸の耳に入っているのかもしれない。
でもでも。
「そりゃそうだよ。だって鶴丸が精魂込めて作ってくれたものなんだから早く見たい」
「だからだ。毎日八つ時が過ぎるまでは開かないからな。俺が呪(しゅ)をとかない限りは絶対に開かないから他の奴に頼んでも無駄だぜ」
「俺がって、え?これ手動で解いてるの?」
「手動というのは語弊があるが……ほら、いいから早く書類を進めたらどうだ? 今日はそれが済むまで開かないぜ?」
結局、今日の分の箱が開いたのは、夕食を終え、お風呂まで済ませた後のことだった。
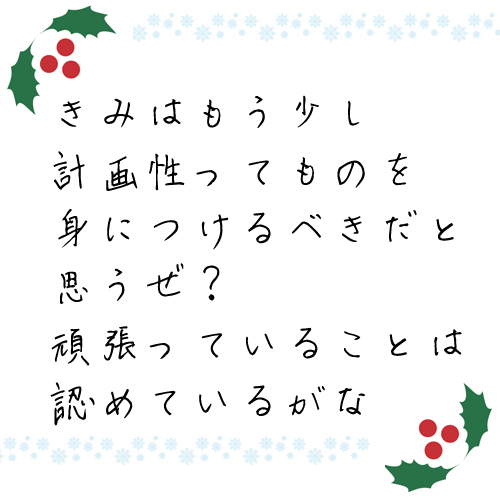

夕餉の前に私室に寄ると、今日の箱が開けられるようになっていた。
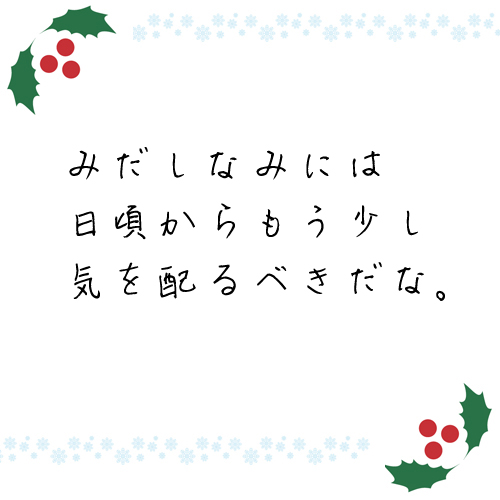

「君はまた……」
櫛を胸に抱えたまま駆け込むように広間に行くと、食欲をそそるおいしそうな匂いで満たされている。ちょうど膳を持ってやってきた歌仙に見咎められて、ごめんなさいと笑って誤魔化す。
ざっと視線を走らせれば、いた。
広間での食事時の席は指定席ではないものの、なんとなくいつもの場所というのが決まってくる。そして、鶴丸の左隣が私の場所だ。
いつも右隣に続く光忠や伽羅がいないのは、今日は彼等が厨当番だからだろう。
「鶴丸、ありがとう」
「ん? ああ」
「可愛いね、これ。大切に使うよ」
「お気に召したなら何よりだ。でもな、主。あれについてはいちいち礼はいらないぜ?」
確かにアドベントカレンダーには毎日何かしら仕込まれているのだから、その都度お礼を言うのも変かもしれない。それでも、こんな風にいかにも贈り物という態のものを鶴丸に貰えたのは嬉しくて、ついつい頬が緩んでしまう。
ふと膳に視線を落とす。今日のメインは筑前煮だ。
鶴丸の膳と見比べれば可愛い花形の人参はこちらの皿にしか入っていなくて、私がここに座ることを見越しての配膳だというのはわかるのだけれど。
「きみ、何してるんだ」
「大丈夫だよ、まだ箸つけてないから」
「そういう問題じゃない」
「ささやかなお礼だよ、お礼」
「お礼ってきみ、明らかに人参を押しつけてるだけだろう」
三つあった花形のそれをすべて鶴丸の皿に移し終え、やれやれと箸を置く。
「人参は栄養たっぷりなんだよ。ビタミンだかカロチンだか…忘れちゃったけど、とにかく体にいいんだよ」
「だったらなおさらきみが食べるべきだな」
言うが早いか綺麗な箸さばきで、移動させた人参が次々に戻されて来る。
うぅ、煮物の人参は嫌いなんだけどな。おかえり人参。
「待ってまって、なんか増えてるよ」
「気のせいじゃないか?」
そう言って箸を置いた鶴丸は、くしゃくしゃと私の髪を混ぜるように撫でてにんまり笑い、「体にいいならしっかり食べないとな」とまるで子供に諭すように言ってくる。
あからさまな子供扱いは面白くないものの、大きな掌で撫でられたのは嬉しくて。
「いいよいいよ、好きな人がくれるものなら説教カードでも人参でもありがたく受け取りますよ~だ」
そう言って口を尖らせると、白い神サマは軽く眉をあげ、どこか呆れたような視線を寄こす。
「なに?」
「いいや、好きだ好きだと、よくもそうすらすらと……。それだけ言ってれば大概減るんじゃないか」
薄く笑うこの男はちっとも全然わかっていない。
確かに私なんて全然相手にもならない小娘だろうけれど、だからってこの想いまでとるに足らないと軽く思われるのは面白くない。
「減るわけじゃないじゃん」
だからすぐに抗議の眼差しでむぅと睨んで言ってやる。
「減るわけないじゃん。溢れて増えすぎて胸がぎゅうって苦しくなっちゃうから言ってるんだよ。言わずに溜めすぎたら潰れちゃうよ」
「ふーん……」
一瞬真顔になった鶴丸は、軽く眉間に皺を寄せるとそのまま視線を外してしまった。
そりゃそうだ。私がどれだけ好きだろうとも、やっぱりそれは鶴丸には関係がないことなんだから。
知ってるけど、なくならないんだから仕方ない。
「……鶴丸には迷惑だろうけど」
「そら、とっとと食べようぜ」
私の言葉などなかったように、いただきますと手を合わせる鶴丸に、後はもうため息しか出ない。
人参は、いつもよりももっとずっとまずかった。
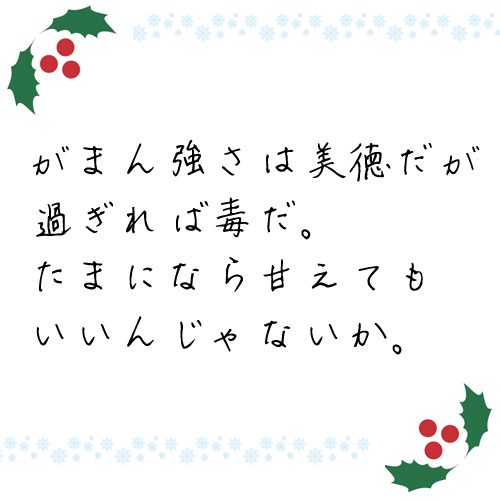
「これは少しは俺に甘えろ的なメッセージかな」
珍しく昼には開いたアドベントボックスにはカードとイチゴ飴が二つ。
執務室の机に並べたそれをまじまじと見つめて口にすれば、知るか、とすげない声が返る。
「じゃあ、この飴を一緒に食べようぜ的な?」
「本人に訊け」
初期刀サマが冷たい。
「だって鶴丸遠征なんだもん」
そう遠征で本丸にいない。それなのにボックスが開くだなんて、これは遠隔操作も可能なんだろうか。
「あんたがそういう風に指示を出したんだろう。それよりいいのか? 今日は早く終わらせてつりーだのいるみ、いる……」
横文字を言い淀む切国をちょっと可愛いなんて思いつつ、イルミネーションね、と助け船をだす。
「そうだ、早くやって本丸をクリスマス態勢にしなくっちゃ!」
去年はここでの生活にいっぱいっぱいで、広間にクリスマスツリーを飾る程度しか出来なかったけれど、今年は違う。庭にもたくさんの電飾を飾ってクリスマス気分を満喫しようという目論見だ。
「あるじさん、終わった?」
「先にデコっちゃっていい?」
乱と加州がひょっこりと廊下から顔を覗かせた。可愛らしい飾り付けなら、このふたりに任せておけば安心な気がして頼んだけれど、せっかくなら私も一緒に飾り付けたい。
「待って待って! あと少しで終わるから! 一緒にやろ」
「……あと少しどころじゃないんじゃないか?」
生温かい切国の視線に曖昧な笑みを返し、今度こそ集中しなくちゃと端末のキーを打ちまくった。
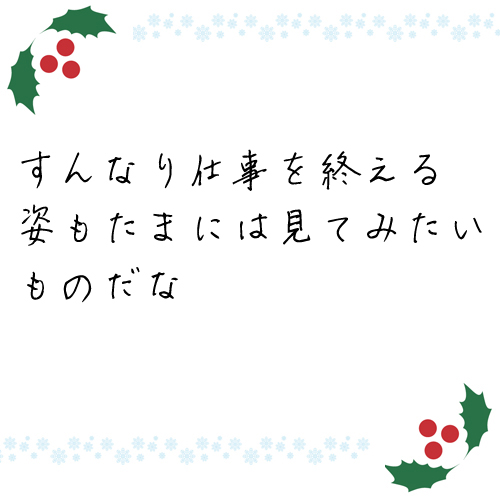
あと十センチ高さが足りない。
背伸びして、精一杯手を伸ばしても目標の場所に届かない。
ジンジャークッキーのオーナメントを手に、ぐぬぬと唸りながらやはり横着せずに諦めて踏み台を持ってくるべきかと思っていると、背後からひょいと白い手が伸びてきた。
「ここでいいのか?」
「そうそう、ありがと」
振り返れば刀を担ぐように持った鶴丸と五虎とが、飾り付けた廊下の壁を興味深げに見廻していた。
「手合わせ終了?」
「はい」
「お疲れ様、あっちにおやつがとってあるよ」
そう言って五虎のふわふわの髪を撫でて上げると、「ありがとうございます」とはにかむように微笑む。
可愛い……クリスマスには天使の羽でもつけてくれないかな。絶対に似合うと思うんだけど。
「随分様変わりしたな」
「とてもきれいです」
「ふふーん。イイ感じでしょ」
昨日から始めた本丸クリスマスデコレーションは、母屋の方はほぼほぼ終盤だ。
きらきらのモールをかけたり、そこにサンタやトナカイ、星や天使といったクリスマスらしいオーナメントをいくつも飾り付け、かなり華やかな仕様となった。
本当は室内も電飾でピカピカさせたいと言ってみたんだけれど、「そこまでの予算はさけんばい」と本丸の財務大臣に却下された。
「こういうのは当日だけやればいいんじゃないのか」
「せっかく楽しい雰囲気なのに一日二日じゃもったいないよ。みんなとワイワイ飾り付けするのも楽しいしね」
「一理あるな」
金色の眼差しを廊下の向こうに投げて、瞳を和ませた神サマは刀で肩をとんとんと叩きながら頷く。その視線の先では粟田口を中心に手が空いてるみんながここと同じようにオーナメントを飾り付けていた。
「庭の方も、今日明日で終わらせるつもりだよ」
「ずいぶんな気の入れようだな。仕事もそのくらい熱心にやれば毎度月末にひぃひぃ言わないで済むんじゃないのか?」
「ちゃんと今日のお仕事終わらせました。……戦争中に不謹慎かなとは思うけど、楽しめる範囲のことは楽しみたいじゃない」
「まあ戦の最中とはいえ日常に彩りがあるのは悪いことじゃないと思うぜ」
「でしょ? 現世だとね、この時期はもう街中がイルミネーションだらけでね。どこに出掛けても浮かれた雰囲気で……」
ハロウィンが終われば街は一気にクリスマスカラーへと移行する。頭の中は学期末テストを飛び越えて、クリスマスから始まる冬休みの楽しい算段をする。そんな時期。
「帰りたいか?」
気遣わしげな視線に、ううんとかぶりをふる。そこまで感傷的になっているわけじゃないし、今だってひたすら楽しいんだから。
「帰りたくないわけじゃないけど、あ、でも鶴丸と歩きたいかな。」
「現世をか?」
「現世っていうか、まあそうだね。クリスマスのイルミネーションの中を歩いてみたい。鶴丸も好きだと思うんだよね、ああいうの。すっごく綺麗なんだよ」
見てきたように口にはしても、私も大抵はモニタ越しに見るばかりで、あまりそういうところに行ったこともない。
ただ、そんなところを好きな人と歩くのはすごく幸せな気持ちになるんだろうなと憧れていただけだ。
「くりすます、なあ……異教の神の生誕を祝う祭りじゃなかったか。もっとこう祈りを捧げるとかそういう祭事じゃないのか」
「元はそうだろうけど……っていうか、その宗教を信じてる人にはそれはもう大切な日かもしれないけどね。ほとんどの人はクリスマスを理由に楽しむ日だよ。恋人だったらふたりで逢って、お泊まりしたりとか」
「へえ……したことあるのかい?」
「な、ないよ。だから鶴丸としてみたい」
「……」
胡乱げな視線に、自分がかなり恥ずかしいことを言ったと気付き、顔の前で大きく両手を振って「違うよ」と釈明した。
「うっあ、その、お泊まりってことでなくて、手を繋いで歩いたりとか、そういうのだよ」
「俺ときみは恋人同士だったか?」
「……違う、けど」
「だよなァ?」
「いぢわる」
上目遣いに見上げてみても、白い神サマはからかうような視線を投げてくるばかりだ。
「あのぅ、ぼ、ぼくはあっちを手伝ってきますね」
「あ゛」
遠慮がちにかかる声に、そういえば五虎がいたことを思い出した。
ごめん、本当にごめん。
「待って、五虎! ここで一緒に」
小さな背中は「馬に蹴られると困りますぅぅぅ」とそのままパタパタと廊下の向こうへと走り去って行った。
今日は朝からすごく頑張って仕事を終わらせた。
宗三には毎月くりすますがあったらさぞや仕事がはかどるんでしょうねぇと呆れたように言われてしまうほどに頑張ったのは、今日こそ庭のイルミネーションの準備を終えて、夜には点灯式をしたかったからだ。
それなのに、昼に降り出した雨はやむ気配もなく、準備すらもままならない。
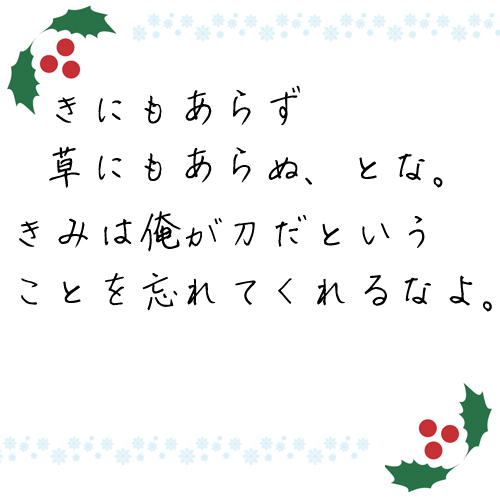

今日のアドベントカレンダーにはカードとチョコレートが入っていた。
私室の畳に転がって、イチゴ味の甘いそれを口の中で転がしながら、カードの文字をもう一度目で追ってみる。
『鶴丸国永』は刀だ。鶴丸は刀で付喪神で人間ではない。そんなことはわかっているけれど、触れればあたたかい彼を。声をかければ応えてくれる相手を。
やっぱり『刀』だとはうまく飲み込めない。
飲み込めなくとも、一瞬気が遠くなるほどに血まみれで帰ってくる彼等を手入れでなおせてしまう度に、『人』とは違うんだというのも思い知っているつもりだ。
「それって念押しするほど重要なこと?」
ぽつりと漏れた声に応える者は誰もいない。
「主~、やんだけどどうする?」
厚の声に起き出して、四つん這いで障子を開ける。廊下に立つ短刀は「ほら」と親指で己の背後を指さした。
雨はやみ、雲の切れ間からは淡い水色と柔らかな薄日が射している。
それに。
「ね、厚。厩当番はまだ戻ってないよね?」
「あ? ああ、一兄たちならまだだな」
「ちょっと行ってくる。戻ったら作業しよ」
飛び起きて縁の下に置いてあった濡れたサンダルに足をつっこむ。そのまま庭をつっきって、厩目指して大急ぎで駆けた。
早く早く。急がないと。
気ばかり急くのに、サンダルとぬかるんだ土では思うようには駆けられない。
それでもどうにか厩についた頃には、軽く息が上がってしまった。
「おや、どうされましたか?」
薄暗い厩をのぞき込めば、ちょうど水を汲んできた一期と行き会った。
「一期、お疲れ様。鶴丸いる?」
「鶴丸殿なら」
「なんだ、主……って、きみ、泥だらけじゃないか」
厩の奥から飼い葉桶を手にしてやって来た鶴丸は、私の足下に目を落とすとそう言って眉を寄せる。
「あ、鶴丸! ちょっとこっち、こっち来て」
「は?」
「早くっ」
手招きして、厩の外へと呼び出した。
「お、やんだな。よかったじゃないか。これならいるみねーしょんの……」
「いいから、ほらっ!」
空を指さすと、金色の目が軽く瞠り、次に弧を描いた。
「ほぉ、虹霓か」
「綺麗でしょ」
「きみ、この為に駆けてきたのか?」
「そうだよ? ふふ、綺麗だよねぇ」
「……ああ、そうだな」
綺麗なものを見つけたら、見せたいって思う。
おいしいものを食べたら、一緒に食べたいって思う。
そんな時には刀だとか人だとかってことは関係なくて、ただただ真っ先に浮かんでしまうんだよ、鶴丸。
「ありがとう」
大きな掌が私の頭をかき混ぜるように撫でてくれる。こそばゆい気持ちで微笑むと「ところでな」と金色が悪戯げに細められた。
「俺は今まで馬糞の片付けをしていたんだが、まだ手を洗っていないんだ」
「げっ! ちょ、やめ、離して」
「なに、ほんの感謝だ。もっと撫でてやろう」
「やめて~」
これでもかと泥をはねさせて追いかけっこをしたせいで、後から鶴丸とふたりで洗濯当番にしこたま怒られた。
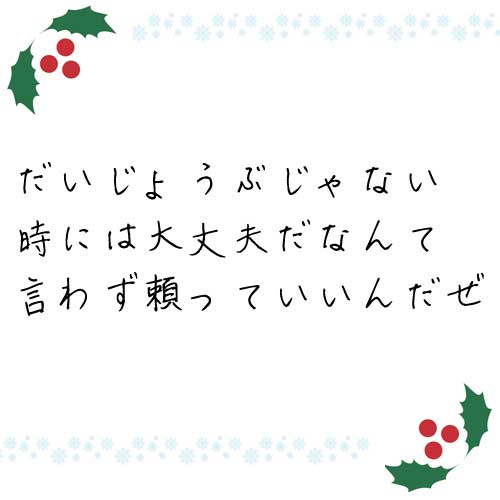
お風呂上がり、濡れた髪を拭きながら私室に戻るとアドベントカレンダーのボックスが開くようになっていた。
髪を拭いていたタオルを首にかけ、はやる心を抑えてクラフト紙を剥いでいく。
今日はカードだけかな。
いつもの柊のそれに目を走らせ、心臓がどくんと嫌な音をたてた気がした。
「え……?」
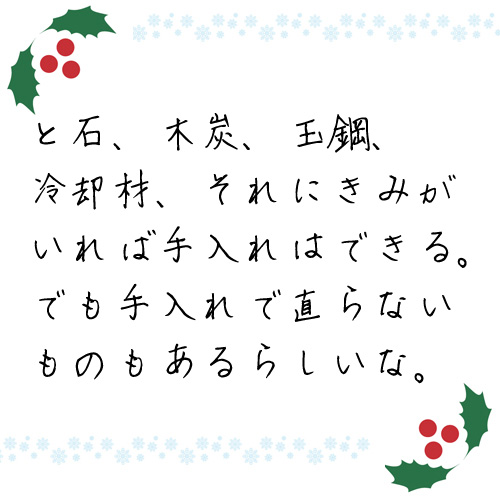
派手な足音をたてて廊下を駆けると、今剣と行き会った。
「あ、いまつる! 昨日の手入れの後、大丈夫?」
「あ、あるじさま?」
袖を捲り上げて、派手に斬られていた二の腕を確認する。手入れの後同様傷跡ひとつないけれど、他にどこかおかしいところはないかと撫でたり体の向きを変えてみたりとせわしなく視線を走らせながら「いまつる、手入れの後どこか変だったりする? なおってないとこない?」そう尋ねると、不思議そうに小首を傾げた短刀は、「はい、みてのとおり、どこもなんともありません」と答えるとニカリと笑った。
「どうかしましたか?」
「う、ううん、そか、いまつるがなんともないならいいんだ。ね、鶴丸知らない?」
「だてのへやで、さかもりしてるとおもいますよ」
「ありがと」
短く告げて、再び駆け出した。
誰かと行き会う度に、手入れで直し足りないところはないか、不調なところはないかと確認しても、皆一様に不思議そうな顔して首を振るばかりだ。
ならば、手入れで直せていないのは鶴丸だけということだろうか。
「鶴丸!いる!?」
勢いよく障子を開け放つと、光忠と貞、伽羅と鶴丸とがなにごとかと目を丸くしていた。
「鶴丸!どこか悪いの!?」
「はあ?」
すぐ傍に膝をつき、袖を捲り、袂を開き、その白い肌に異常がないかと確認する。触ったり、撫でたりしても、特段異常は見当たらない。
「あ、主、さすがに女の子がそれはちょぉっと……」
「なんだみっちゃん、ヤボなこと言ってねぇで、俺たちが移動しようぜ」
「待てまて、貞坊」
立ち上がりかけた貞の袖をひいた鶴丸はこちらに向き直ると「きみはきみで、いきなり随分積極的だなァ?」などと口の端を引き上げた。
「だって、鶴丸が手入…」
「っと、おい! まだ濡れてるじゃないか」
言うが早いか肩に掛けていたタオルを手にする。
「これも濡れてるな」
「ちょっと待って」
すぐに立ち上がった光忠が手拭いを出しきてくれると、それを受け取った鶴丸はガシガシと私の髪を拭き始めた。
「ちょ、鶴っ、か、髪はいいから」
「よくない。夏じゃあるまいし、こんなんで風邪でもひいたらどうするんだ」
「それより貞、光忠、伽羅、鶴丸っ、手入れで直せてないとこない?」
「なんだ急に」
それまで黙って成り行きを見守っていた伽羅が口を開いた。
「これ! みんなは大丈夫?」
カードを翳すように見せると、三人をそれに目を走らせた後、じっと鶴丸を見つめる。鶴丸はといえば、髪を拭く手を止め、ばつが悪そうに視線をそらした。
「あー……すまん。これは、それだ」
「それって? どこか調子悪いの?」
「すまんすまん。そういう話しを聞いたことがある、とな。それだけだ」
「本当に?」
「ああ」
「本当に本当?」
「本当だ。悪かった。だからきみは早く髪を乾かしてきた方がいい。襟元も濡れちまってるじゃないか」
言われてそっと襟口に手を伸ばせば、確かにしっとりとしてしまっているような気もする。
クリスマスを控えたこの時期に、風邪で寝込んでいる暇は一日だってない。
「とりあえず、大丈夫ならよかった。ごめんね、楽しんでいるとこ邪魔しちゃって」
そう言って立ち上がると、きっちり乾かせよと念を押された。
あー、びっくりした。でも、みんなも鶴丸もなんでもないんだったら本当によかった。
「なあ」
出て行きかけた背中に呼び掛ける。
「きみ、カードも全部とってあるのか?」
「当たり前でしょ。鶴丸がくれたものなんだから。……ごめんね。お邪魔しました。おやすみ」
そう言ってひらひらと手を振って出て行く背中を口元を引き締めて見送ると、三人分の視線がこちらに注がれていた。
誤魔化すような笑みを浮かべ、「光坊のずんだは今日も旨いなあ。な!伽羅坊」と呼び掛けてみても、視線は逸らされ、あからさまにため息をつかれる。
「そういう顔を主にももっと見せてあげればいいのに」
「そういう顔?」
「やにさがったそういう顔だよ」
「そう言ってやるなよ、みっちゃん。男心ってやつだろ」
「それにしたって……。だいたい鶴さん、手入れで直せないものって、それ」
「おっと、光坊。それ以上は言ってくれるなよ?」
「はっ、面倒な男だな」
伽羅坊はそう言うと、気に入りの酒をなみなみと杯に注いだ。
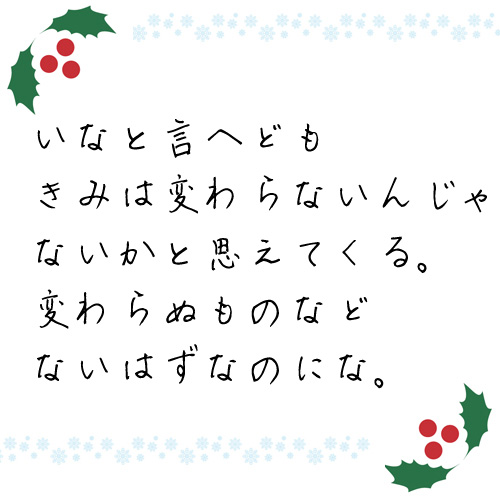

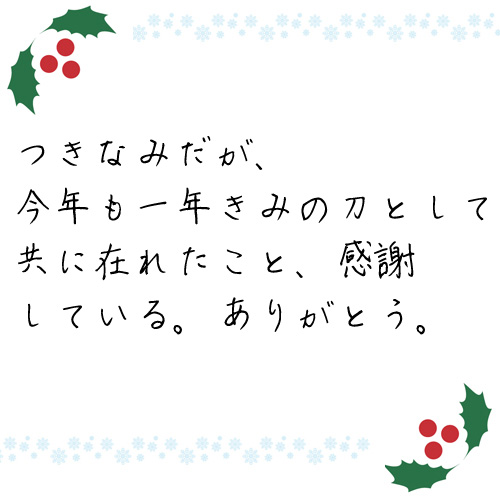
「鶴丸~、いる?」
「……いる」
あまりに静かで、扉一枚向こうにそぉっと呼び掛ける。
いつもならどうということもない橙色の裸電球が、今夜はやけに頼りなく感じて、不安はじわりとわきあがる。
「鶴丸?」
「いる。どこにもいかない。いいから早く、いや早くなくてもいいから、呼び掛けるのはやめてくれ」
急いで手を洗って扉を開けば、廊下の壁に寄りかかって待っていた鶴丸は、呆れたような視線を寄こした。
「ごめん」
「いいさ。主殿の護衛も刀の務めだ。それが厠の行き帰りのためだとしてもな」
「うぅ、ごめんって」
ようやくすべての設置を終え、今日はイルミネーションの点灯式だった。いつもよりもはしゃいだ気分で夕餉の後もすぐには私室に戻らず、十人ほどで映画を見た。
短刀たちが多かったから、てっきりコメディかアクションものでも見るのかと思いながら観ていたのに、日本の少し古めかしい屋敷が舞台のそれはどうにも雲行きがアヤシくて。
がっつりホラーだと気付いた頃には途中で切り上げる方が却って後から怖い気がして、最後まで観てしまった。根本的には何も解決していない、随分と後味の悪い結末を。
こんなことなら涙目で一期の元へと走った五虎に付き添うフリで、私もあの時に切り上げてしまえばよかった。
私室に入って冷たいお布団にもぐりこんでも、真っ暗にするのは怖くって常夜灯もつけたまま。掛け布団から手足がはみだそうものなら、得体の知れない何かに掴まれそうな気がして、縮こまるようにして寝る努力をしていたというのに、よりによってトイレに行きたくなってしまった。
そうしてビクビクしながら冷たい廊下を踏みしめていたところに、鶴丸に行き会ったのだ。
「なんだおどおどして。後ろ暗いことでもありそうに見えるぜ?」
「ちょっとトイ、厠へ」
「ああ、そりゃ呼び止めて悪かったな」
そう言ってそのまますれ違おうとした鶴丸の袖を、恥を忍んでひいた。ついてきて、と。
「ありがと」
「まあ構わんが。これに懲りたらほらあ映画はやめておくんだな」
「ホラーだって知ってたら見なかったよ」
「それにしたって、そもそも人間はきみしかいないこの本丸で、今更何がそう怖いんだ?」
少し前を行く鶴丸が肩越しに振り返った。整った白い横顔が、庭に散りばめられた色とりどりの光にほんのりと照らし出される。
普段は21時には消す約束のそれは、初日の今日とクリスマスだけは23時までつけておくことになっていた。
「お化けとか幽霊とか、得体が知れないのは怖いよ」
「ふうん、俺たちだっって十分得体が知れないと思うがなァ。ああ、そんなに怖いなら添い寝でもして寝かしつけやろうか」
「いいのっ!?」
期待満点に声を上げると、白皙の美丈夫は「冗談に決まっているだろう」と顔をしかめた。
「デスヨネー」
ふと、鶴丸が足を止めた。庭を見遣る彼につられるように視線をやれば、トナカイの鼻が赤く光り、その周囲は光の花畑のように煌めいていた。
「綺麗なもんだな」
さっきまではひと気のないそこは明るくとも不気味に思えたのに、今ここに鶴丸がいてくれるというだけで、星が降りてきたように見えるんだから不思議だ。
「ふふふ~、そうでしょ? これをみんなにも見せたかったんだ」
「ふうん、みんな、な」
なんとなく声が低くなった気がして、イルミネーションから鶴丸に視線を戻せば、金色のそれはこちらに向けられている。
「な、なに?」
じっと見られるいわれもなく、もしや私の背後でも見ているのかとそっと振り返ると、鶴丸は再びすたすたと歩き出した。
「え、え、鶴丸、なに?」
「いいや? なあに、きみの背後に何かがいたって、声でもあげれば誰かが駆けつけるさ」
「ちょ、怖いこと言わないでよ」
鶴丸の早足は、私室に着くまで緩むこともなかった。
←とうらぶ目次へ戻る