Pawooとネタ違いで開催した鶴さにアドベントカレンダーネタのログです。
Repaint the Christmas 1
Repaint the Christmas 2
Repaint the Christmas

これまで経験したすべてを覚えているかと訊かれたら、それはないと即答する。
例えば3才の頃に連れて行って貰ったらしい家族旅行は、旅館の玄関にあった大きな水槽と金魚しか覚えていない。
小学校の入学式は覚えていないけれど、校庭の隅、一年生の教室のすぐ前にあった小さな池。そこに小便小僧が居たことは覚えている。休み時間になると、その池を飛び越えて遊ぶのが楽しかった。
高校生の時、友達との寄り道で好奇心で食べた日本酒のジェラートの味。おいしくないと笑い合ったあの味を好むようになったのはいつからだったろう。
断片的な記憶は、それでも確かに連なっていて今に繋がる。
埋もれた欠片も、すれ違った人が纏う香水や、久し振りに袖を通した服や、そんな何かに誘発されて唐突に思い出す。
だから、忘れているように思えて、実際は私の中に眠っているだけという記憶も多いんだろう。
前世の記憶もそんな風に、いつの間にか深いどこかかから顔を出し、そうか、あれも私だったと腑に落ちたのは中学にあがってすぐの頃だったと思う。
今の自分が見たことも聞いたこともない記憶が、確かに経験したものとして内に息づいているのだと自覚した時、そんなものを持って生まれてきたことにひどくがっかりした。
もうこの先、まともな恋なんて出来ないだろうと思った。
恋を、していた。毎日毎日、みんなに主として大切にされながら、馬鹿みたいにたったひとりを追いかけていた。
今になってわかる。たくさんの刀剣の主として誰より平等であるべき審神者が、たったひとりを特別大切に想うのは、あまりに幼くて愚かだった。
主にあるまじき行いだと怒られてもよさそうなものなのに、本丸のみんなは小娘だった私の所行を苦笑ひとつで受け入れて、優しく見守ってくれていた。
親元を離れ、友達とも会えないような日々をそれほど寂しく感じないで済んだのは、みんなのお陰だった。
時間遡行軍との戦い。それが命のやりとりをする危険なものだということは、人ならば生きているはずもないほどの怪我して帰ってくる男士を目にしてわかっているつもりでいた。むせ返るほどの血の臭いに吐きそうになりながら、泣くのを堪えて手入れをする度に「大丈夫だ」と笑ってくれた神様たち。
そんな戦の真っ直中でも、花見だの西瓜割りだの、芋焼きパーティだのと何かにつけては本丸をあげてのイベントを愉しむ。うちはそういう本丸だった。
ある年のクリスマス、私は現世のイルミネーションを庭に再現したくて予算の限り実行した。
本丸のみんなに、冬の冴えた空気の中で星と違って色とりどりに輝くそれを見せてあげたいという気持ちと。
大好きな鶴丸と、あわよくば恋人のように手を繋いで光の中を歩いてみたいという邪な願いと。
アドベントカレンダーを貰ったのは、その年のことだった。
懲りることなく毎日毎日好きだといって自分を追い回す雛鳥に、退屈しのぎを渡すような、そんな気持ちだったんだろうか。
あの年に限って彼が私にそれをくれた理由はわからない。
ただ、五条がくれたのと同じように、そこには毎日カードと小さな贈り物が入っていた。
カードに書かれていたメッセージの全部は覚えていないけれど、まるで謎かけのようなよく意味のわからない言葉や、小言のような文面に毎日毎日一喜一憂、ううん十喜一憂くらいで宝物を与えられたように浮かれていた。
昨日五条が寄越したあのカード。あれは、鶴丸がくれたメッセージの中のひとつと同じだった。あれだけは私の中で強く焼き付いていて、忘れられるはずもない。
『明後日ふたりで答え合わせをしよう』
それは何を意味するんだろう。
五条も鶴丸の記憶を持っている。そんなのは答え合わせをしなくたって、あのカードを見ればわかる。
私が覚えているかを確かめたいんだろうか。
それならば、いっそスマホに幾つも投げてくるそれで訊けばいいのに、昨日からとりとめなく送られてくる言葉は、このカードがなかったなら彼がそうだとは気付かないほどにいつも通りの五条だった。
それらすべてをスルーしていることに痺れをきらして電話を寄こさないあたり、彼の中でも答え合わせは済んだはずだ。
それでも懲りずにメッセージだけは送ってくるそれも、朝の挨拶を最後に途切れている。
向こうも大概忙しいのか。それとも──。
出勤してしまえば、やらなければいけないことに追われているうちに時間が過ぎる。そうして余計なことを考えないようにして一日を過ごしたというのに、帰って来てしまえばただこうして座り込んで、立ち上がる気にもならない。
化粧も落とさなければいけないし、昼も食べずに過ごした胃が何か入れろと訴えている。
でも、どうにも動く気にはなれなかった。
五条は何がしたいんだろう。
彼がくれた言葉全部が嘘だったとは思いたくない。思いたくないだけで、本当は全部嘘かもしれない。わからない。
そもそも、あれがアドベントカレンダーに仕込まれていたということは、11月の終わりのあの日には五条は思い出していたということだ。それなのに、ただの一度もそれらしい素振りなど見せなかったのが、『彼』らしく思えた。策を巡らすあの刀は、いつだって涼しい顔で、時には味方だって欺いて誉れを持ち帰っていたのだから。
ふいに震えたスマホがテーブルをカタカタと叩き、思わず肩を跳ねさせた。
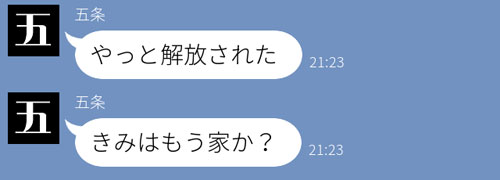
お疲れ様と返しかけて指が迷う。
昨日から幾度もそんなことをしている。
他愛のない言葉に、いつものように返せばいい。
たったそれだけのことが、もうひどく難しかった。
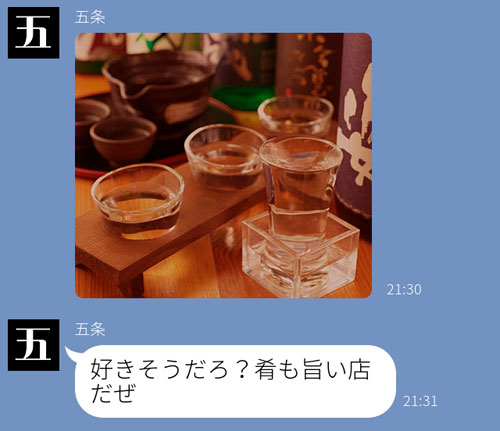
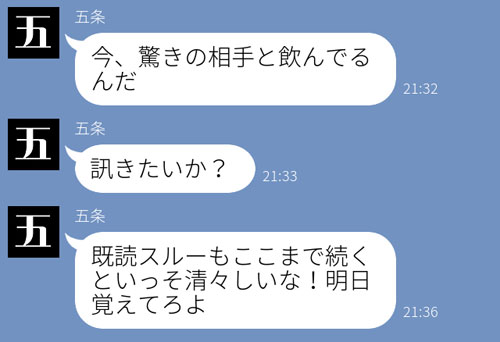
明日。
明日本当に答え合わせをするつもりなんだろうか。
重い息を吐いて、立ち上がる。
とにかくシャワーを浴びて化粧を落とさなくちゃ。そうでなければ眠ることも出来ない。
眠れるんだろうか。昨夜ろくに眠れなかったことを思い出しながら、もう一度ため息を落として浴室へと足を向けた。
音も振動も切って放っておいたスマホは、朝にはひくほどに着信履歴が連なっていた。
誰かと愉しく呑んでいる風だったし、明日覚えていろよなんて言ってくるくらいだから、もうこんなに何度も電話をしてくる用事なんてなかったろうに。
それでも、本当に急ぎの用件ならばそんな文言があってもよさそうなのに、10回を越える着信履歴以外に送られているメッセージはたったひとつ。
『頼むから出てくれないか』
何かあったんだろうか。
心配なのに、通知画面にあるこのメッセージが既読の表示に変わったら、こちらが送信するのを待たずに電話が鳴りそうな気がして怖じ気づく。
画面をタップしかけた指先をそのままに、3呼吸分ほど迷ってからスマホの電源を落とした。
本当に何かあったなら、私なんかに連絡を寄こしてる場合じゃないはずだ。
呑んでいるうちに興がのったとか、きっとそんなことだろう。
『明後日ふたりで答え合わせをしよう』
その明後日がきてしまった。
内容のインパクトに忘れていたけれど、今日はそもそも忘年会だ。
元々がクリスマスを期限にきってのことだったから、それは12月24日か25日のことなんだろうと決めてかかっていて、それについて五条に確認をとることはしないままでいた。
けれど、今年のイブは日曜日だ。社会人カップルのクリスマスは、もしや今夜を指すんだろうか。
いやいや、そんな決まりもないだろう。
そうは思っても、今日は忘年会に出席しない組からは絶対に残業しないぞという確固たる意志を感じた。なにかにつけて席を立ってはなかなか戻って来ない女子社員も、煙草休憩の多い男性社員も今日は朝から真面目に手を動かし続けている。
パタパタと端末を打つ女性陣がいつもの3割増しで綺麗な気がするのは、きっと気のせいではない。
五条は出張から帰ったんだろうか。以前聞いた話しでは、今週いっぱいはあちらだったはずだけれど。
アドベントカレンダーは11月に仕込んだものだ。
出張が後から入って、五条の心づもりと変わってしまったのかもしれない。
とはいえ、昨夜は『明日覚えていろよ』と言っていた。それならば、やはり五条は今日会うつもりでいるんだろう。
先延ばしにしたい気持ちが強いものの、一度は向き合わなくてはいけないことだ。それが最後だとわかっていても、自分が撒いた種なんだから仕方ない。
朝イチで忘年会の会費だけ払うから欠席させて欲しいと幹事の席まで言いに行くと、雨の中に捨てられた子犬のような目で理由を尋ねられた。
「体調が優れなくて」
嘘ではない。寝不足だし、食欲はないしで、いいとはいえない状態だ。なにより気分的に、愛想笑いで飲みの席数時間をやり過ごすのはかなりキツイ。
「確かに、顔色が良くないですね。大丈夫ですか?」
いや、大丈夫じゃないからこうして言いに来たんだけど。
なんて言えるはずもなく。
気遣うようなことを言って眉を寄せた幹事君は、じゃあ顔を出すだけでもいいです、お酒は飲まなければ大丈夫。鍋だから胃にも優しいですよ、などと結局欠席を認めてはくれなかった。
幹事をきちんと勤め上げられるかどうかは地味に上司陣にチェックされている。間接的に評価に関わるともなれば、幹事君もそうやすやすと人数が減らす許可など出せるはずもない。そう考えてしまうと、欠席を強行するのも申し訳ない。
昼休みになったら。
午後になったら。
仕事が終わったら。
五条への連絡をずるずると先延ばしにしたまま、忘年会が始まった。
居酒屋の座敷フロアを貸し切ってのそれは、聞いていた通り女性の参加が見るからに少ない。
ここのところあまり食べていなかった胃に、揚げ物のオンパレードは重かったものの、安いコース料理の割には野菜もたっぷり入った寄せ鍋は優しく染み渡った。
同時にお酒も染み渡り、常の許容量の半分も呑まないうちにお酒がまわっているのを自覚していた。
審神者をしていたあの頃は、日本酒どころかお酒自体おいしいとは思わなかった。
男士がみんな、時には短刀たちまでおいしそうに呑むのを不思議な心地で見つめていた。
あの頃も今くらい呑めたなら、鶴丸と一緒に呑むなんてことも出来ただろうか。
考えてみても仕方のない話しだ。
鶴丸に、恋をしていた。叶わないと知りながら、やめることも出来なくて、好きな気持ちのままに追いかけ続けた。
それに加えて、刀としての鶴丸も信頼していた。
クリスマスを数日後に控えたあの日。
新しい歴史改変が確認された戦地。そこに赴く一番隊に私の本丸が選ばれたという通知が届いた。
特別な任務を与えるべく選ばれた本丸。
政府のそんな世辞にまんまと踊らされ浮かれていた私は、任務の内容を聞いた時の鶴丸の様子が常とは違っていたにも関わらず、一番刀だからという信頼を振りかざし、隊長に任命した。そうして、深く考えることもなく送り出してしまった。
送り出した6振のうち、戻ってきてくれたのが5振。
クリスマスイルミネーションに彩られた本丸の庭。浮かれた景色の中、転位装置の門から己の血で真っ赤に染まって乱や今剣が帰還した姿を、今でも時々夢に見る。
ひとり、またひとりと帰還する中、一番刀だけは二度と戻らなかった。
鶴丸は、ううん、私以外はその任務がどれほど危険なものか、帰って来られない可能性がどれほど高いかを把握していた。無知な私だけがそれに気付かず、彼を殺してしまったのだ。
選ばれたとは名ばかりの一番隊が持ち帰った情報のお陰もあり、うちの本丸は大層評価された。
でも、そんなのはただ虚しいばかりで。
鶴丸が遺したアドベントカレンダーを前に、自分の愚かさを噛みしめ続けた。
そもそも女としてなんて見てもらえなかったのは仕方ないとしても、主としても期待に応えられないどころか、最期には呆れ果て、恨まれていたって不思議じゃない。
だから、五条に初めて出逢ったあの日。私に一瞥もせずすれ違っていった姿に、安堵した。
私にはもう霊力なんてカケラもないくせに、彼がそうだと、どこかの鶴丸国永なんかでなく、あの鶴丸だということもわかってしまった。
前世で一方的に結んだ絆は切れていなかったらしい。
絆といえば聞こえはいいけれど、元を正せば木に家畜を繋いおく綱のことだという。ならばそれは文字通り、心を繋がれたままの絆の為せる業なんだろう。
五条はといえば、容姿の変わってしまった私に気付かないのか、それとも覚えていないのか。
親しく接するようになって、物言いの端々で彼は覚えていないのだろうなと決めてかかった。
『五条国永』であって『鶴丸国永』ではない。
それが、免罪符だった。
忘年会が無事に終わり、やっと解放されるとホッとしながら店の外に出た。
このまま三々五々解散となるが、二次会に参加する社員はこのままここに残って、改めて二次会のお店に移動する。
「今日はまだあんまり呑んでないじゃないか。行くだろ?」
とっととこの場から立ち去ろうと考えていると、すっかり出来上がった直属の課長が赤い顔で話しかけてきた。課長とは部署の飲み会で何度か一緒に呑んでいるせいで、私がお酒が強い方だというのはバレているし、日本酒がイケル口だというのも知られている。だからこそ、サワーをちびちび呑むようなことをしているのが不思議に思えたんだろう。
「今日はもう失礼しようかと」
温かい店内から、一気に寒風に晒される外へと出てきたせいか、それともやはりいつもよりお酒がまわっているのか、少しだけ舌がまわりにくい。
それでもどうにか引きつる愛想笑いを浮かべると、「またまたぁ。まだ全然呑み足りないだろ」などと笑われてしまった。
「いえ、今日はホン……」
「申し訳ありません、この後は約束がありまして」
背後から手首を捕まれるや、彼の声が響いて咄嗟に肩を竦めた。
「お! 五条くん戻って、……え? きみたち、そうなの?」
「はは、今必死で口説いてるところなんです」
どこか遠くにその声を聞きながらも、掴まれた手首だけが熱かった。柔らかな物言いで課長と話すのに反して、絶対に離さないという確固たる意志をそこから感じて痛いほどだ。
「よく言う。聞いたよ? あの案件纏めてきたんだって?」
「お陰様で。……すみません。では彼女も一緒にこのまま失礼します」
軽く一礼した男は、怖くて顔を見ることも出来ないまま固まっている私の手首をぐいと引いて足早に歩き始めた。
知った顔が数人、驚いたようにこちらを見ている。
あの五条国永が女と手を繋いで歩いている。端からはそう見えるだろうか。
でも実際は捕まえられて連行されているようなものだ。
「ちょ、待っ……」
私の手をひいて歩く速度は、出てきた店から離れるほどに加速していくばかりだ。
彼にすれば少し足早に歩いている程度かもしれないけれど、そもそもコンパスが違う。私にとってはなかば小走りに近かった。
目の端に映るイルミネーションは、クリスマス前の最後の週末を謳歌する人波を映し出す。
酔って浮かれたサラリーマンのグループや、視線を合わしては笑み交わす恋人たち。店先ではサンタやトナカイが客を引き、時には声を張り上げている。
そうして、こちらを振り返ることもなく強く手首を掴んだまま前を歩く白銀の髪。
出張帰りそのままなんだろうか。鞄を手にするチェスターコートの背中に、白い羽織が重なって見える気がした。
色とりどりの光の中。折り重なる符号に視界が揺れて、息をするのもままならない。
「待っ、待って。早……ご、っ」
五条、と。
呼び掛けようとして躊躇する。
今、ここに居るのは誰だろう。
五条なのか。鶴丸なのか。
それとも、どちらの名前も呼ぶことを許さない男だろうか。
「スマホ」
「……」
「切ってるのか? 何度も連絡した」
不機嫌を隠そうともしない低い声を発しながら、それでもようやく少し緩やかになった歩調に、自分の息が軽く上がっているのに気付いた。
酸欠になりそうな頭の中で、たった今言われたことを反芻する。
「スマ、ホ……」
鸚鵡返しに口にすれば、ようやく肩越しに振り返った金色と目が合う。
口を開きかけ、込み上げる吐き気に咄嗟に手で口を覆った。
「!!」
軽く体を折れば、掴まれていた手首が解放された。吐き気をやり過ごすように、息を細く吸って吐いてを繰り返す。
「大丈夫か? そんなに呑んだのか」
先程までの怒気が霧散した気遣う声に応えたいのに、何か話したら吐きそうで、緩く首を振るにとどめた。
唾を飲み込み、幾度か呼吸を繰り返すうちに少しおさまって来た吐き気に視線をあげれば、金色の瞳とその背後には光のアーチが映る。緩やかな点滅に、収まりかけたそれを呼び覚まされる気がして、急いで視線を落とした。
「吐きそうか?」
「だいじょぶ、だから……静かなとこで、休みたい」
目を伏せてから言ったそれが、誤解を招く発言だと気付き「そうじゃなくて」と口を開きかけたその時。
チっと舌打ちをした男は苛立たしげに髪をかき上げた。
そうでなくとも怒っている相手に、不興を買ったと思わず身を縮こませる。
「いや、これはきみじゃ……とにかく移動しよう。歩けるか?」
「ゆっくり、なら」
「ん、わかった。吐きそうになったら言えよ」
いつものように、いや、いつもよりももっと柔らかな声音にもう一度視線を上げると、金色とまっすぐ目が合った。
「主」
懐かしすぎるその呼び掛けに、瞬時に体が固まる。
鶴丸に幾度となく呼ばれたその呼び声は、夢の中ではいつだって冷たく突き放すような音をしていた。
冷えた指先から、今度こそすべての熱が失われていく心地で立ち尽くす。
目の前に居るのは、私が殺した男だ。
断罪の言葉を待つ耳に響いたのは、やけに大きなため息と、駄目だなという呟きと。そうしてそのまま男の腕の中に抱き込まれる。
五条の、香りだ。白檀の甘さとも違うその香りをゆるりと吸い込んで、体を強張らせたまま、抱き返すことも逃れることも出来ずにいると、「きみが好きだ」と囁かれる。
少し前まで胸を高鳴らせたその言葉を、今はどう受け取ったらいいのかわからない。
「知らなかったとはいえ、俺は勘違いしていた。そこはこれからゆっくり答え合わせをするとして、だ」
答え合わせ。その台詞に思わず体が小さく震えた。すると、私を捉えていた腕が緩み、顎を取る手がこちらを見ろと促す。恐る恐る顔をあげれば、視界はこの男だけしか映らない。
寄せられる顔にキスでもされるかと思いきや、額を合わせられ、焦点も結べないほど間近から瞳を覗き混まれた
「きみが好きなんだ。だから今日は観念してお持ち帰りされておけ」
そそのかすような甘い声に、もう否とは言えなかった。
散らばった意識がたゆたうように寄り集まりながら、輪郭を描き出す。
いつもよりも大きくて柔らかな枕に埋もれるように眠りながら、起きるのは嫌だと無意識に拒む。
目を覚ませば、そこは彼がいない現実だ。
誰も私を責めなくて。
それどころか、みんながいつも以上に優しくしてくれる。
さぼってばかりでは終わらないよ?と窘めていたはずの歌仙に、無理は禁物だと仕事を取り上げられ、寝坊をしても、眠れたんならそれでいい、と切国は瞳を和ませる。
食事は私の好きな物ばかりが並んだし、少し遅くまで起きていると光忠が野菜スープやホットミルクを持って来てくれた。
私のせいなのに、はっきりとそう言ってくれる男士は誰ひとりいなかった。
気遣われるのが苦しくて、逃げるように業務に没頭した。
やらなくてはならないことをしている間は、余計なことを考えずにいられたから。
そうして泥のように眠りに落ちても、やっぱり朝が来てしまうのだ。鶴丸のいない世界の朝が。
ひたひたと近づく足音と気配とを感じていると、ギシリとベッドの傾ぐ感触があった。
髪に触れる感触は心地よくて、誘われるように重い瞼を押し上げる。
いつものストライプとは違うブルーグレーの枕。どうして違う色なんだろうと考えてもなお、撫でる感触はやまない。それは誰にも触れて欲しくはなかった心の深い場所にまで容易く入り込むように染みこんで、溢れ出た。
「……泣いているのか」
労るような声と共に、目元が拭われる。
そうか、私は泣いているのか。
だって。
「だって、鶴丸がいない……」
視線を巡らせれば、ベッドの端に腰掛けた男と目が合う。一瞬だけ痛ましげに細めた目は、すぐに弧を描き、「そうだな」と肯定する。鶴丸そのままの姿で。
「……え?」
ひとつ瞬けば、瞳から押し出されて眦から滑り落ちていく感触がする。急いで目元に指先をやれば、泣いていた。
「え? へ?」
知らない枕。知らない部屋。そして、スウェット姿で首にタオルを掛けた五条がいる。
「なっ」
飛び起きると、軽く瞠った金色は「おお、いい眺めだな」とニヤリと笑う。
長袖のTシャツ、下は──パンツだけ。
「!!」
急いで布団をかぶりなおして丸まりながら、顔だけ巡らして五条を見上げた。
混乱した頭のまま、記憶を手繰り出す。
昨夜。
ほとんど口をきくこともなく、手をひかれて歩いた。
何を話したらいいのかもわからなくて、ただ、スマホの電源を切ったままだったことを怒られた。
駅に戻る途中、運良く捕まえたタクシーで五条の住むマンションに直行して。
酔っていたのか、本当に不調だったのかわからないけれど、とにかく部屋につくなりトイレで吐いて。
心配されながら、シャワーを借りたところまでは覚えている。
「さてはきみ、覚えてないな?」
熱い顔を意識しつつも五条を見つめていると、「いやあ、きみは酔うとあんなに積極的になるんだな」と悪戯げに目を細める。
「──!?」
まさか、覚えていないだけでイタしてしまったんだろうか。
いやいや。でも記憶が飛ぶほど飲んではいないし。
そうは言っても、実際問題覚えてはいない。覚えていないけれど、私が積極的に迫るだなんて芸当が出来るとも思えない。
「うそ、だよね?」
「……どっちがいい?」
意地の悪い返しに、うぅと呻けば「冗談だ。きみがシャワーを浴びてそのまま脱衣所で撃沈したから、寝かしてやっただけだ」と軽く肩をすくめて見せた。
シャワーを浴びて。脱衣所から記憶はない。温まった体にいよいよ酔いがまわったのか、裸のままへたり込んで。
つまりは拭いてくれたのも、着せてくれたのも、この男ということだろう。
視線を逸らして枕に顔を埋めると、「ま、役得というよりは軽く拷問だったな」とわざわざ耳元で囁かれた。
「ほい、とりあえず飲め」
差し出されたのはペットボトルの水だった。そうして差し出されてみれば、ひどく喉が渇いているのに気がついた。
「ありがと」
掛け布団をひっぱって下半身に巻き付けながら身を起こす。
受け取ったペットボトルは常温で、だからこそ一気にごくごくと流し込むことが出来た。
「二日酔いってこともなさそうだな」
「う、ん」
「さて、どうする?もう一度シャワーでも浴びてすっきりするかい?」
そう言われて初めて、五条の髪が濡れていることに気がついた。彼はシャワーを浴びてきたらしい。
「シャワーは、いいや。あの……私の服」
「ないな。洗濯中だ」
「っ、ないって……」
「待ってろ。きみが着られそうなものを見繕ってくる」
私をひと撫でした五条は、すぐに別の部屋からウエストを紐で絞れるハーフパンツとパーカーを持って来てくれた。
彼の部屋は2LDKはありそうだ。ダイニングに置かれたテーブルと、その向こうにはテレビの前に置かれたソファーと小さなテーブルと。
五条の普段の生活を垣間見るように感じながら、促されるままにダイニングの席についた。
朝食にと用意されていた中華粥は、お店で食べるのと同じくらいおいしかった。
ふわりと香る生姜と鶏ガラスープは絶妙で、疲れ気味の胃にも少しも負担なくおさまっていった。
器用そうに見えるこの男は、料理の腕前まで相当なんだろうか。
私が知る鶴丸は、卵焼きも炒り卵のように崩し、焦がしていたはずだったのに。
けれど、そんなことも口には出来ず、核心に触れることはなにも話さないまま、食後に淹れてくれた緑茶を持って、ソファへと移動した。
腕が触れそうな距離に並んで座るのが、なんとなく居心地が悪い。かといってあまり離れて座るのもわざとらしい気がして、少しだけ体をずらして距離をとった。
「さて。訊きたいことがあるんだが」
ふーふーと湯飲みに息を吹き込んでいると、唐突に核心をつかれ、茶を跳ねさせそうになった。隣を見ることも出来ず、そのまま固まれば小さく笑う気配がして湯飲みを取り上げられた。
「きみも、俺に訊きたいことがあるだろ」
湯飲みがなくなり手持ち無沙汰になった両の手をぎゅうと握り合わせ、そこに視線を落としたまま「ある、よ」と答えた。
「いつ、わかったの」
「それは、俺が鶴丸国永だったってことか? それとも、きみが主だったことか?」
「……両方」
声が震えてしまう。それでも訊きたくて、手の甲に爪を立てながら答えると「こら」と手をとられて握り混まれてしまった。
私の表情を窺うように覗き混む心配そうな顔は、すぐに苦笑へと変わった。
「主、とな。もう呼ぶ気はない。昨日は試したくてそう呼んだだけだ」
「そう呼ばれるに値しないってことは、ちゃんとわかってるよ」
「なんでそうなる。……いや、違うな。俺が悪い。ひとつずつ話すか。俺がいつ前世を思い出したかってことなら、先月だな。なんの拍子だか、朝目が覚めたらわかっていたな」
「……」
「で、きみが前世で何者だったかわかったのはな、それと同時だった」
「な、んで」
そんな素振りは見せたつもりもない。容姿だって、物の考え方だって、彼の知る私ではないはずだ。それなのに。
「なんで、か。そうだなァ。俺にもわからん。ただ、そうかと腑に落ちた。最も、本当に確信したのは、あのカードを仕込んだ日以降、だな。きみの反応で、間違っていなかったとわかった。」
『たいがい嫌いにならないか』
あのカードは、試す意図もあったのか。私は狙い通りに反応して、自ら素性を明かしてしまったらしい。
「他には?なんでも答えるぜ」
ふると首を振る。彼が『鶴丸国永』だというなら、そうして彼が私を何者かわかっているならば、私がすべきは訊くことじゃない。
「ない、よ。ただ、ごめんなさい。謝って済む話しじゃないけど……あの時の『私』は無知で無計画で無鉄砲で。あなたに嫌われて当然だったよ」
はあ、とため息が耳を打つ。握られた手が解かれ、叱られるのを待つ子どものように俯いたままでいると、そのまま抱き込まれた。
「きみはいつ前世を思い出した?」
なぜ抱き締められているのかわからないまま、思考を巡らせて「中学生、くらい、かな」ぎこちなく口にすると、髪を撫でる手が一瞬止まった。
「それは、長かったな……」
「……」
「俺は、いや鶴丸はな。例え戻れなくとも、きみはすぐに立ち直って、また誰か好いた相手を見つけて嫁いでいくだろうと思っていたんだ。そんな相手を得たきみが、今生でもその相手が忘れられないでいたとしても、それでも今度こそ口説いて俺のものにしたいと、そう思った」
「……え?」
見上げると、「呆れたかい?」とばつが悪そうに笑う。
呆れるも何も、言われた意味がわからない。
私が誰を好きになるって?
今度こそ?
「それじゃあまるで鶴丸が私を好きだったみたいに聞こえるんだけど」
「あのなあ……。好いてたさ。きみがいう無知で無計画な主を。雛のようについてまわるきみを、誰よりも愛しく思っていた」
「う、そ……だって、私が、私が鶴丸を殺したのに」
両頬を挟まれて無理に視線を上げさせられる。間近で瞳を覗き混まれ、やわらかな口調で、けれどきっぱりと「違う」と否定した。
「それは絶対に違う。そんな風に思っていたから、だからきみは……。馬鹿だなあ」
私をぎゅうと抱き締めた男は「きみのせいなはず、ないじゃないか」と繰り返した。
「本音を言うなら、前世なんざ思い出さない方がよかったんじゃないかと思ってたんだ。でも、やっぱり思い出せてよかったな。そうじゃなけれりゃ、きみの間違いをただすことが出来なかった」
「間違い……」
「ああ。……だが、これだけは言っておくが俺は前世のことなんてひとつも関係なくきみを好きになったんだからな」
「……男として意識されないところが新鮮だっただけでしょう」
五条と呑むようになってすぐの頃、こう言っちゃなんなんだが、と前置きした彼は、すぐに恋愛対象にされちまうから、女友達ってのは居た試しがないと笑った。
「きみは、そういうとこだけは自分の前世を見習うといいぜ。あの無駄に前向きだった雛はどこに行ったんだろうなァ。
ま、そういうところもかわいいんだが」
言うが早いか、ちゅっと音をたてて唇にキスを落とす。
「!」
「そのぶんじゃ、雛乃舞なんて酒がないってことも気付いてないな」
カードに書かれいた酒の名前だ。ネット検索しても見つからなかったその酒が、ないというのはどういう意味だろう。
「カードは全部見たかい?」
こくりと頷く。
「とってあるか?」
「そりゃ、もちろん」
その答えに満足げに唇の端を引き上げた男は「それは重畳」と言いながら唇を重ねてくる。
「む、ん、ちょ……、っん、ふっ、待……」
差し込む舌に応えることなく話そうとする私に、不服を顔に張り付かせ渋々唇をはなした五条は、訊くなら早くしろと言わんばかりに「なんだ」と息がかかる距離のままで問う。
「雛乃舞がないって……カードがどうしたの?」
「まあ大した意味はないな」
「気になる」
「気にするならもっと他のことにしてくれ。例えば、このままソファでもいいか、ベッドに移動すべきか、とかな」
「──っ!」
「我ながら昨日はよく我慢したもんだ。いい子でオアズケしてたんだ。そろそろご褒美があってもいいよな?」
ひそり、と。
息を吹き込むように耳元で下の名前を呼ばれ、首を竦める。
「過去の答え合わせはもう仕舞いだ。これからの話しをしようじゃないか」
「……話す気なんかないくせに」
精一杯の虚勢で睨むと、喉の奥で笑った男は「否定はしないな」と囁いて、再び唇を重ねてきた。
今にも眠りに落ちそうていきそうなのを堪えるように、しきりに目をしばたたかせていた腕の中の彼女は、「息、苦しいからヤダ」と拙く呟くとクルリと体を反転させて、こちらに背を向けてしまった。
「つれないじゃないか」
ぼやこうとも、それすら聞いているのかいないのか。
滑らかな背中を俺の腹に押しつけるようにもぞもぞと動くと、やがて満足したように長く息を吐いて、そのまま眠りへと駆け下りて行ってしまった。
ほんの先程まで熱を分け合った肢体は、今は互いをあたためあう穏やかなぬくもりがひたすら心地よい。
このままでは目が覚めた時には不快だろうから体を拭くくらいはしてやりたい気もするが、ぴったりと寄り添う素肌の感触が離しがたくて動く気にもなれない。
片腕でやわい体を抱き込みながら、もう片方の腕を枕に彼女の顔をそっと覗き込む。
愛しい女を手に入れた幸せを噛みしめながらも、少し腫れた目元は痛々しく映る。後で濡れたタオルをあててやれば、起きる頃にはマシになるだろうか。
こういう時は冷やすんだったか、あたためるんだったか。
『あの時の『私』は無知で無計画で無鉄砲で。あなたに嫌われて当然だったよ』
力なく頭を垂れる彼女を、ただ抱き締めた。
ほんの一ヶ月前に思い出したのとは違って、彼女は中学生の頃には前世を思い出していたのだという。
多感な十代の頃に、そんな記憶はどれほどに重かったことだろう。ましてや、己を死に追い込むほどの記憶というのは──。
殺した、と彼女は言った。
あの日、俺が戻れなかったことで自身を責め続け、深く傷ついたままの彼女に、何をどう言い連ねてやったところで届かない気がした。
どれほど愛しく思っているのかを知らしめたかった。
もっとも、もうそれすらも言い訳で、ただ愛しい存在を一刻も早く抱いてしまいたかっただけだったようにも思う。
今朝、夢うつつに泣いていた彼女は「だって、鶴丸がいない……」と途方に暮れた声音で呟いた。
あれ以降、主は泣かなかったと聞いたが、きっと違う。
そんな風に泣くことすらも許されないとでもいうように、それを身の内に押し込めていたに過ぎない。
現に、行為の間、理性がすっかり溶けた頃には彼女は子どもみたいに泣きじゃくっていた。
彼女の中にはあの日のままの雛がいて、傷を癒せないままにひとりで蹲っていたのだろう。
湧き上がる愛しさに、眠る彼女を抱き締める腕に力を込める。
『減るわけないじゃん。溢れて増えすぎて胸がぎゅうって苦しくなっちゃうから言ってるんだよ。言わずに溜めすぎたら潰れちゃうよ』
庇護すべき雛だとばかり思っていた彼女。
千の齢を生きた付喪神として、可愛い人の子を支えてやれねば、守ってやらねばと思ってはいたが、あんな年代で刀剣男士というかりそめとはいえ命を預かる役目はさぞや重圧の日々だっただろう。
そんな日々の中で、笑って過ごすというのはその実並大抵のことではなかったのではないか。
「確かに、俺はきみを見くびっていたんだろうな」
囁いて頭を撫でてやったところで、体力を使い切っているであろう彼女が答えるはずもない。
最期の時。
還るなら本霊なんかでなくあの本丸に──あの子の元に還りたいと願った。
だから、こうして還ってきたのだろう。
誰より愛おしい彼女の元に。
彼女の肩口に鼻先を埋めるようにして口づける。
もう幾つも付けた印を、またひとつ刻みつけた。
明日の朝。きみが目を覚ましたら、アドベントカレンダーを開けようじゃないか。
クリスマスはここで過ごすと決めていたからな。
きみに渡したあれには入れなかったんだ。
そして、今度はきみが、カードの答えをくれないか?
12月24日


←とうらぶ目次へ戻る