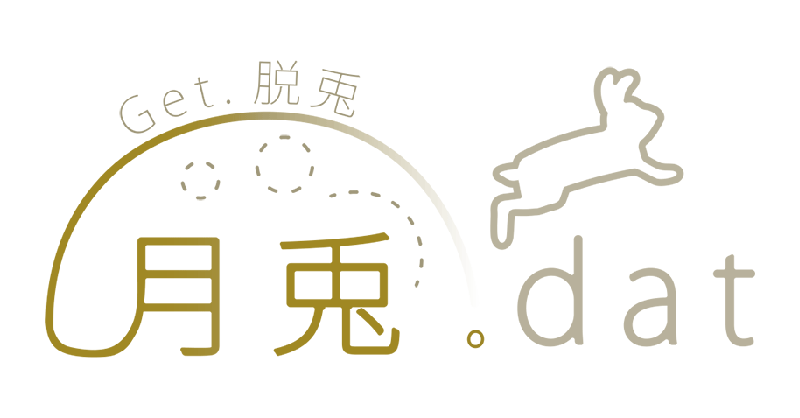格子から差し込む月光が、うっすらと影を落とす。陽が昇れば、また地面は熱く照らされるのだろう。
少女は木枠の向こうに見える、満月を過ぎた月をぼんやりと見遣る。
連れて来られたのは、村長の家の離れの小屋だった。中央に囲炉裏があるだけの室内は清潔に整ってはいたが、これといった物が置いてあるでなくひどく殺風景だった。
がらんとした室内のその向こう、土間の引き戸の外には見張りが数名いるようで、なにごとかぼそぼそと話している気配はするが、もうその会話の内容に興味をひかれることもなかった。
夜が明けたら、みおは『神様』に捧げられるのだ。
「馬鹿みたい」
村人は、みおを神様に捧げるという。けれど、当の神様は見返りなどなくとも雨を降らせようと天つ彼方に出掛けているし、なにより彼自身が『花嫁』など望ん ではいないということを、少女は誰より知っているのだ。ならば己は、いったい何に、何の為に捧げられようとしているのか。
態のいい厄介払いではないか。そんなことの為に殺されてなんかやらない。そう思って、昨日捕まってから幾度も脱走を試みた少女は、腕も足も傷だらけだ。
先ほど女たちがやってきて、みおを綺麗に洗い上げていった。温んだ水がそれらの傷にひどく沁みたが、少女はただされるがままに汚れを拭われていた。
タライの水に浸かるよう促された時、璃卯を呼んでみようかと思った。彼はタライでは駄目だと言ったけれど、もしかしたらと考えたからだ。でも、出来なかった。
璃卯が、天帝に降雨を願った後ならばまだいい。けれど、もしもそれがまだ済んでいなかったとしたら。そして、みおの声に彼が応えて戻ってきてしまえば、雨を降らせることは叶わない。そうなれば、村人は迷わず社を壊すに違いないのだ。
『社を壊したくないのであろう?』
幾度も逃げだそうとするみおに夕餉を持ってきた村長は、ぽつりとそう言った。
『お前さんを花嫁に捧げれば、村の衆も少しは気が収まる。今すぐ社を壊すとは言わんだろうて』
社を壊しさえしなければ、きっともうあと数日のうちに雨が降る。必死の思いで老人に訴えたみおに向けられたのは、怪訝そうな眼差しだった。
『儂らはの、怖いんじゃ。お前が言うことは本当かもしれない。社の神が雨が降るよう努めてくれているのかもしれん。だが、みお。お前の言うそれは、本当に神なのか?』
どれほど言葉を尽くしても、結局は信じて貰えないのだと悟った。
あとはもう、ただ黙って項垂れるしかなかった。
『社は守ってやろう。お前が嫁いだら、7日は誰にも触れさせん。どうじゃ?』
残酷な言葉は、ひどく優しい声音で紡がれた。
みおが命を捧げても、社の安全は7日しか守られない。それでも。
(それなら、璃卯が言っていた半月には足りる)
社を守ることができる。それだけが、今のみおの救いだった。
やがて、空が白み始めた。塒から起き出した鳥の囀りが空を渡る。
いつもなら起き出して身支度を調え、畑仕事を始める頃だ。でも、もうそんな朝はやってこない。
「本当の花嫁になれるなら、よかったのにね」
枯れたと思った涙が、再びほとりとこぼれ落ちた。
泉までは、輿で運ばれた。
花嫁行列をそれらしく仕立てる為か、花嫁が逃げ出さないようにする為か。いずれにしろ、みおは逃げる気はなかったし、逃げられるはずもなかった。
みおは生まれてこの方、袖を通すどころか見たこともないほどに上等な衣を身につけていた。真っ白なその衣装は、銀糸で様々な花の刺繍が施されている。輿を 運ぶ者たちのひそやかな囁きで、これが村長の孫娘の為に仕立てられたことや、本当ならばこの花嫁の役目を負うのも村長の血縁者なのだということも知った が、不思議と嘆きも怒りもわいてはこなかった。
(私が、璃卯を守る)
身につけた衣装の豪華さとは裏腹に、みおの右足には麻縄が巻かれ、その先には大きな石がくくりつけられていた。さながら罪人のようだ。それでも少女の胸にあったのは、己が大切な者を守ることができるという誇らしさだった。
輿は泉のほとりに静かに下ろされた。
輿の後をついてきていた村人たちが、少女と泉とを取り囲むように並ぶと、村長が懐から恭しく巻紙を取り出し、泉の神へと雨乞いを始めた。これが終われば、みおは水に飛び込まなくてはならない。
足にくくられた石は、泉の傍に置かれた。その横に佇みながら、いつものように澄んだ水面を見下ろせば、決めたはずの心が揺らぐ。歯の根があわないほどに震え出すのを、ぐっと奥歯を噛みしめて堪えた。
泉に映る己は紅をひかれ、見たこともない女のようだ。美しい着物に身を包み、悲壮な眼差しをこちらに向けている。
後ろ髪を束ねるのは、浅葱色のあの結い紐だ。支度をする女たちが髪を整えてくれようとした時も、これだけは譲らなかった。
(璃卯……)
泉に沈めば、戻ってきた彼がきっと真っ先に見つけてくれるだろう。
何事かと驚くだろう。もう1度、あの別れの時のように抱きしめてくれるだろうか。
さらさらとした触り心地だった、白銀の髪を想う。この衣の刺繍糸なんかよりも、もっとずっと繊細な輝きをしていた。
繋いだ指先を思い描く。つれない言葉とは裏腹に、いつだって優しくしっかりと繋いでくれた。
たったひとり誰よりも大切な存在を守れるならば、もうそれだけできっといい。
「よいか? みお」
いつのまにか口上を終えたのだろう。村長の問う声に顔をあげると、泉に集まった村人たちがじっとこちらを見つめていた。
座り込んで念仏を唱えている老人や、なにが起こるのかわからないとばかりに指をしゃぶって首を傾げている幼子、ニヤニヤと笑う男や、哀れむような眼差し。それらを見回したみおは、彼がいつも腰掛けていた大岩を振り返った。
いつものように足を投げ出して座る璃卯が「馬子にも衣装じゃな」と笑ってくれたらいいのに。
こんなこと全部が、夢だったらよかったのに。
そっと瞼を閉じて、大切な姿を思い描いた。
(璃卯。水を通して声が届くなら、あなたの声も私に届く?)
声が、聞きたかった。もう一度、彼の「みお」と呼びかける声が聞きたかった。
「みお」
けれど聞こえてきたのは、しわがれた老人の、早くしろと急かす声だ。
怖くて怖くて堪らない。でも今この社を守れるのは──璃卯を守れるのは私だけだ。
(私が、璃卯を守るの)
そう考えると、わずかばかり心が凪ぐように感じた。
璃卯、璃卯。
伝えたい言葉がある。
あなたがいたから寂しくなかった。
あなたがいてくれたから、私はひとりぼっちじゃなかった。
じりと、慣れぬ草履で足を踏み出す。
璃卯がいてくれたから、私の心は冷えきることなどなかった。
この次生まれるなら、人じゃないものがいい。
想いを告げるのを躊躇わないで済むように。
あなたの掌にもらわれた蝶のように、ずっと傍に寄り添っていられるような、そんなものに生まれてきたい。
(ううん、本当はなんでもいい。ただ、もう1度会えたらいいな)
最後の息を吸い込んで、彼に繋がる場所へと身を投げた。
──璃卯?
──みおかっ?
──うん
──いかがした!? 水に落ちたか!?
──大丈夫。水に……水に浸かっているだけ
──ひとりでか。珍しいの。村はそこまで暑いか。
──……うん。
──待っておれよ。これからようやく天帝に目通りじゃ。明日にはきっと戻れる。もうすぐ雨を降らせてやるほどにな。
──よかった。それなら間に合う。
──なんじゃ?
──ううん。……うん。待ってる。ずっとここで待ってるよ。
──もうすぐ帰る。もうすぐじゃ
──うん。璃卯、あのね……。
──なんじゃ?
──……。
──……みお?
──……だい……すき、よ
明くる日のこと。
夜が明けても村に光が射すことはなく、頭上には真っ黒な厚い雲が蠢いていた。やがて鋭く走る稲光を合図にしたように、ザッと雨が降り出した。
始めは歓喜に沸いた村人たちも、いつまでたってもやまぬ雨に右往左往しだした。
吹きすさぶ風は獣の吠え声のようで、増えて溢れた川は龍のごとくうねって地を這い、逃げまどう人々を次々に飲み込んだ。
夜が来て、朝が来て、再び夜が来ようともまだ嵐は収まらない。
かろうじて丘の上の社に逃げた者たちも、お堂の屋根をもひきはがしそうな勢いの雨風に、ただ身を寄せあって震えるしかなかった。
この社も、こんな風雨に曝されてはそうは保つまい。誰もがそんな風に思いながら身を縮ませていた、その時。薄ぼんやりと泉が光り出した。沈めた鬼子が仕返しにやってくるのではと、人々が固唾を飲んで見守るその先で、光はどんどん強くなる。
ややして泉の中央からゆっくりと幾重にも波紋が広がり、淡く光る紫の蝶が飛び立った。
誰もが呆然とそれを見つめる中、頼りないはずのちっぽけな蝶は、強風にあおられることもなく天を目指して飛んでいく。
蝶の飛んでいったその先から雲は切れ、一筋の光が差す。それは嵐の終わりを告げる光だった。
濁流は村を押し流し、多くの人を飲み込んだ。けれど、なぜか人柱になった少女の住んでいた家とその畑は、嵐などなかったように彼女が生きていた頃そのままに綺麗に遺されていた。
生き残った村人は、古びた社をきれいに修繕すると、少女の為に小さな塚をたてた。
その塚には、花の咲かぬ冬にもひとひらの花が添えられていたという。
「化けて……でてくるのではなかったか?」
呟きに答えるはずの少女は、もうどこにもいなかった。