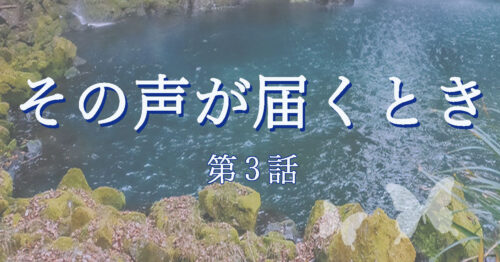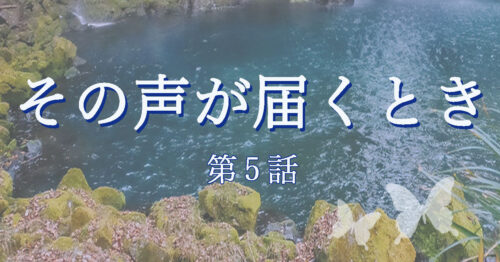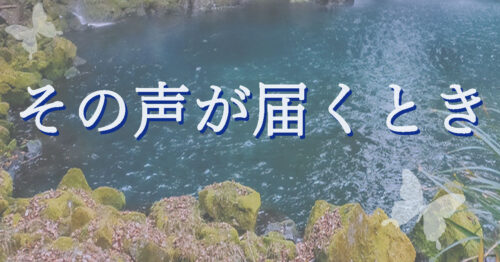「ふぁあぁ……」
いつものように岩の前に座った少女は、大口をあけてあくびすると、たてた膝に眠そうに顔を伏せた。
柔らかな陽射しに透ける新緑は、あっという間に青々と力強く茂り、まもなく彼女がこの村に来てから3度目の夏が来る。出逢った頃は幼さの残る顔立ちだった少女も、近頃はふとした表情が大人びてきた。それでも、こんな風にあくびをする様はまだどこかあどけない。
「眠そうじゃの」
少女の寄りかかる岩の上に座ったまま声を掛けると、首だけめぐらしてこちらを見上げたみおは、眩しそうに目をしばたたかせた。
「うん。昨日、夜中に外でなんか大きな音がしてね。目が覚めちゃったから寝不足で」
「猫じゃの」
即答してやると、みおは少し不思議そうに首を傾げる。
それはそうだろう、と思う。猫ならば、積み上げた桶や農具をあそこまで派手にひっくり返すはずもない。
「猫の声なんかしなかったよ? 猫っていうよりもっと大きな……」
「では狐じゃ。狐が出たのじゃろ」
「うちは鶏もいないし、狐が来そうなものなんてないよ」
「知るか。通りがかったのじゃろ」
「……なにか怒ってる?」
自覚する以上に、声に不機嫌さが滲んでいるのだろう。みおは眉間に皺を寄せると、よじよじと岩に上り、童の隣に腰を下ろした。
「別に、怒ってなぞおらん」
「そう? なら、いいんだけど」
こちらを覗き込むように見ていたみおは、まだどこか納得がいかないという顔だ。
「みお。戸締まりはちゃんとするのじゃぞ?」
あくびのせいだろうか。眦を少し潤ませながら「なに急に」と怪訝そうな顔をする少女に、童は顔をしかめた。
「おまえとて一応は年頃の娘だ。用心するにこしたことはない」
「そんな物好きいないよ」
まったく自覚がないらしい少女は、軽く笑って空を見やり、「梅雨なのに、今日も降らないねぇ」などと呟く。
「いるっ──……かもしれないし、間違いということもあるからの。よいな?」
どうにも危機感のなさそうな表情で、それでも気圧されるように顎をひいた少女に、童は昨日の出来事を思い起こす。
昨夜の騒ぎは猫などではない。猫などより遙かに性質の悪いものだった。
「あの娘、綺麗になったよなぁ」
「化生でなければ、嫁にしてやってもいいくらいだ」
いつものようにみおの家の辺りを散策していた少年の耳に、そんな会話が届いたのは昨日の昼のことだった。
見れば、畑仕事に精を出す少女を、茂みの中に身を潜めるようにして2人の若者が覗き見ていた。
「あれで鬼の子だというのだから、もったいねーなあ」
「単なる噂でねのか?」
「噂だけで、あの薄気味悪いアザが消えるか。阿呆が」
彼らの会話を耳に、童は己の右手に視線を落とした。そこには、紫の蝶が羽を広げている。
よかれと思ってしたことだった。
アザがあるせいで少女が泣くのなら。
その蝶があるせいで、村人が彼女を遠巻きにするというのなら、それを消してやればいい。そう考えただけだ。
けれど童は、それがひどく浅はかな考えだったとすぐに思い知った。耳に入ってくる少女の噂は以前より辛辣になったし、親類の家に身を寄せていたみおは家を出されてしまったのだ。
子供が産まれたら窮屈だろうと思って。
みおは、家を出た理由をそう語った。出されたのではなく、己の意志でそうしたのだと笑って、けして本当のことは語らない。だから彼もそれ以上問うこともせず、そうか、とただ頷いた。
みおは、鬼の子だなどと言われるような不思議な力は何ひとつ持ち合わせていない。強いて言うなら、童の姿が見えるのが特殊と言えば特殊だが、さりとてその他の人外が見えるわけでもなく、大した力ではないだろう。
人外になって数百年余り。これまでも、己の姿が見える者はあったし、言葉を交わす者もいた。ただ、大抵は驚いて腰を抜かすか逃げ出すか、人でないことを蔑 むか。多少のやりとりをしても、すぐに疎遠になるのが常だったから、人間にこれほど全幅の信頼を寄せられたのは初めてのことだ。
出逢った、あの夏の日。
少女は思い詰めた顔をして「化けて出てやる」などと脅しにもならない台詞を口にして、手をつないで欲しいとねだった。
渋々差し伸べた手に、袖から覗いた人外の証──腕を覆う鱗を目にして怖じ気付くかと思ったが、彼女は虹色できれいだと言って、少しも怯むことなく童の手を取った。
(あたたかいのじゃな……)
人と言葉を交わすことはあっても、あんな風に触れあったのは初めてだったから、その温かさに驚いた。柔らかくて、頼りなげで、けれどその皮膚の下には、生命が脈々と力強く通っている。
心もとないような、胸がきゅっと痛くなるような、不思議な感覚だった。
その後も、少女はほぼ毎日、水を汲みに泉にやって来た。
村で見かける時は頼りなげにぽつんとひとりで居ることの多い少女が、丘を上ってきては、年相応の無邪気な笑みで楽しそうにあれこれととりとめもなく話す。素っ気ない返答にもめげることなく話し続ける少女に釣られて、いつしか浮き立つ心地になることも増えた。
童は他の人外と群れて過ごす習慣などない。だから、ひとりで過ごすのは当たり前のことで、それを寂しいとか物足りないなどと思うことはなかったのだ。
けれど、いつしか少女の来訪を心待ちにしている己に気付いた。
そんな風にみおとの時間を快く思うほどに、解せなくなっていくのは村人たちの態度だ。
笑顔も、語る言葉も、行いも、どれをとってもみおはごく普通の人間だ。そんな彼女が、なぜいつも、いつまでもひとりぼっちでいるのだろうか。
(我のせい、かの)
羽ばたくこともない蝶を見つめ考える。
アザをとってやらなければよかったのだろうか。そうしたら、例え時間はかかっても、やがては少女も村人たちに馴染んでいっただろうか。
「生娘だろうなぁ」
舌なめずりしていそうな声音に、ふと我に返る。
「違いない」と頷く男も、下卑た嗤いを口元に刻んでいた。
「ひとり寝は、寂しかろうなぁ?」
「化け物とはいえ、情けをかけて慰めてやるか?」
「ひひ。そうだな。せめてもの情けじゃ。一晩じっくり可愛がってやればええ」
「だが相手は鬼の子だ。大丈夫かの」
「なぁに。見ろ、あの細っちょろい腕。そこらのおなごとそうは変わらん。ふたりがかりで押さえつければ、どうということもなかろ」
「違いない」
男たちは顔を見合わせて、嗤いながら頷きあった。
(あやつらめ……)
懲らしめてやる。そう思った。
けれど、伸ばしかけた手は宙で止まり、そのままぎゅっと握りしめられる。
それは、正しいことだろうか。みおの為になるんだろうか。
童には、人の幸せなどよくわからない。それでも、生き物として生まれたからには、つがいになって、子を為し、やがて死んでいく。それが当たり前のことだろうと思う。
だからみおも早く人と打ち解けて、やがては男と添えばいい。それがみおにとっての幸せに違いない。
だが少なくともその相手は、こんな風に彼女を好奇の目で見つめ、無理矢理に奪ってしまおうなどと企てる輩では断じてない。ない、はずだ。
握りしめた掌をゆるゆると開き、じっと見つめる。そのまま動くことも出来ずにいるうちに、いつの間にか男たちの姿は茂みの陰から消えていた。
とはいえ夜を迎え、いざ忍んできた2人を前にすれば我慢もならず、みおの家にたてかけてあった農具や桶を盛大にひっくり返してやった。その物音だけで、男たちは転がる勢いで逃げ去ったのだ。
「難しい顔をしてるね」
「能天気なおまえとは違うでの」
「むぅ。私だっていろいろ考えてるよ。こないだ蒔いた種がなかなか芽が出ないなぁとか、今年はいっぱい米も野菜も穫れたらいいなぁとか。あとは……梅雨なのに雨が降らなくて大丈夫かなぁとか」
膨れながら指を折りながら話す、その横顔を見つめ考える。
もしも彼らに、少しでもみおへの好意が見えたなら、昨夜のことは見過ごしただろうか。
(無理であろう、の)
きっと邪魔をしただろう。
なにしろそこには彼女の同意がないのだ。例え相手に好意があろうとも、やはりそれではきっとみおが傷つくに違いない。
「笑っておればよい……」
ほろりと零れた呟きに、「え、なに?」と反応を返す少女をじっと見つめる。
出逢った頃より、髪がずいぶん伸びた。すっきりしてきた顎の輪郭も、これからますます大人びていく兆しだろう。
みおは己とは違う。
たった1年で、どんどん成長していくのだ。少女は女になり、またたく間に老い朽ちていく。触れられる場所にいるこの姿も、陽炎のように儚く、脆く、童が到底追いつくこともできない時間を生きている者だ。
手を延べて、少女の顔にかかる髪を指先で耳にかけてやりながら「伸びたのう」としみじみ口にすれば、途端に声を弾ませて「うん! ほら」と向こうをむく。結い上げた髪をこちらに向け「こうして結ってると、大人っぽく見えるでしょ?」と嬉しそうだ。
少女は、こうして大人びていくことが楽しいらしい。それは着々と終わりに向かうことだというのに、なにがそれほど嬉しいのやらと考えながら、ふとそのうなじに視線を縫い止められる。白い首筋に漂うそれは、色づき始めた女の色香だった。
「だから、そのように迂闊なっ」
「ん?」
「だからっ、……そ、そのようなことを尋ねること自体、まだまだ子供だというのじゃ」
童の言葉にまたも頬を膨らませた少女は、ふと思いついたように「ね、ちょっとあっち向いて」と己の反対側を指さした。
「なんじゃ?」
「いいから」
きらきらと輝かせた瞳はいたずらを仕掛けようとする幼子のようで、やはりまだまだ大人にはほど遠いと内心苦笑しながら言われた通り半身をひねって背を向けてやると、さらりと髪に触れてくる。
「……? なにかついておるか?」
「ううん。綺麗だなって。いいなぁ、どこもかしこも綺麗で」
鱗を綺麗だと言う少女は、人の髪の色とかけ離れた白銀の髪をも同じように評するようだ。
童の髪をしばし弄んだ少女は、やがてそれをひとつに束ねた。
「できた。ふふ、お揃いだよ」
再びこちらに背を向けて、己の結い紐を指す。少し褪めた浅葱色には見覚えがあり、おそらくは着られなくなった着物をほどいて作ったのだろう。不揃いな縫い目に彼女の苦心が見てとれて、知らず笑いが漏れた。
「そうか」
「うん」
ほんのり頬を染めた少女を前に、温度のない体に熱が宿るのを感じる。
みおは威勢良く岩を飛び降りると、「そろそろ水汲みしなくっちゃ」と桶を手に泉のほとりにひざまずいた。
彼女の水汲みは、大抵は日に10回ほどだ。
わざわざ丘を上ってくるのではなく、川で汲めば労力も半分で済むだろうにと思うものの、川を恐れる少女の気持ちもわかるので、そう強く勧めることも出来ない。
「みお」
「んー?」
こちらを見ることもなく返事をする少女に、童も岩を飛び降りて歩み寄った。
「礼をやる」
「え? そんなのいらないよ」
袖をめくり、己の鱗を1枚剥ぐ。生爪を剥ぐような痛みが走るが一瞬のことだ。奥歯を噛んで痛みをやり過ごした童は、小指の先ほどの、向こう側が透けそうに薄いそれを「飲め」と差し出した。
少女は桶を急いで置くと、鱗を剥がした場所におそるおそる手を伸ばし、けれど触れるのを迷っているような素振りをする。
やはり改めて目にすれば、みおにとって人外の証など不快なものなのかもしれない。当たり前のことなのに、先ほど鱗を剥いだ時よりも、もっと重い痛みが胸にかかった。
「気持ち悪いやもしれぬが、毒ではないゆえ……」
「……く、ない!?」
「……?」
「こんな、こんなの剥がして痛くないの!?」
「たいしたことは、ない」
「よかった」
心底ホッとしたように瞳を和ませたみおは、鱗を受け取り1度だけ透かし見ると、躊躇なく口に入れた。
あまりに躊躇いのない様子に、こちらが狼狽えるほどだ。
「飲んだよ?」
「毒だったらいかがするつもりじゃっ」
「……? だって、飲めって。毒じゃないって言ったから」
「それは……」
「ねぇ、本当に痛くないの?」
温かな指先が遠慮がちに、羽が触れるようなささやかさで、腕を撫でる。
その感触がどうしようもなく胸苦しく、心許なく、そして──愛おしい。
通ってくるのを心待ちにしていたのも、触れられるだけで胸がざわざわとせわしない心地になるのも、いつもみおが言い掛けてやめてしまう『でも』の先が聞きたいと思うのも、彼女を想うがゆえだ。
(詮無きものを……)
己の腕に触れている少女を見つめる。
出会った頃はまだみおの方が背が低かったはずなのに、いつの間に追い越されたのか、今は少女のほうが指先ひとつ分だけ視線が高い。
指先ひとつ分。たったそれだけの、けれどそれは、これからどんどん顕著になっていく、生きる時間の違いを現す決定的な違いだ。
「大丈夫じゃ。それよりもなにを飲んだのか、少しは気にならぬのか?」
「なにって、鱗でしょ? 味はしなかったよ?」
「誰が味の感想を──……もうよいわ」
ほぉと溜息をついた童は、みおから離れてひょいと岩に飛び乗る。
「先ほどの鱗は、我に繋がるものじゃ。これでおまえが水の中にいる時ならば、我に声が届くようになった。もしも落ちたら、我を呼べばよい。助けに行ってやるゆえな」
「感謝しろ」と肩をそびやかすも、泣き出しそうな少女に気付き、息を呑む。
「いかがした?」
「これからは、川で水を汲めってこと?」
そんなつもりではなかったが、それを考えなかったわけでもない。
たったひとりで、畑仕事をするのは大変なことだ。それに加え、わざわざ丘の上まで水汲みにくるのは彼女にかなりの負担を強いているはずだ。川で水を汲むことが出来るようになるだけで、それはずいぶんと軽減されるに違いない。
「ここまで来るよりも、その方が近くてよかろう?」
「もうここで水汲みするなってこと?」
「川で汲めば用が足りる」
「そうじゃなくて。それは……それはもうここに来るなってこと?」
「……」
そうだ、と答えればいいのだろうか。そうだと答え、だから人を頼り、人に添って生きていくことを覚えるべきだと諭せばいいのだろうか。
今みおには童しかいない。だからきっと、雛が親鳥を唯一の存在としてついてまわるように、依存しているに過ぎない。
こんなに可愛くて、心根の優しい少女だ。時をかければ、村人たちだってみおの本質に気付くだろう。そうすればきっと、みおの対にふさわしい者も現れる。
少女は叱られた子供のようにうなだれ、息を詰めて泣き出すのを堪えている。
「来るなと言っているのではないぞ?」
少しずつでいい。少しずつ距離をとればいいのだ、と。突き放しきれない童は、そんな風に自分の中で言い訳をする。
「水を汲むんでなくとも、来たければ来るがよい」
「うん」
少し濡れた瞳のまま、花が綻ぶような笑みを浮かべる少女に苦笑する。
少しずつ距離をとって、やがては人に馴染むように仕向ける。
そんなことが出来るのだろうか。こんなにも、愛おしいのに。
「だがな、みお。人は……人は人と関わり、人のなかで生きていくものじゃ。ここに入り浸り、我とばかり話しておるものではないぞ?」
諭すように、けれどその実は己に言い聞かせるための言葉だ。
「……」
「早う……早う他の者と馴染んで、良き相手を見つけ、つがいになればよい。そうすれば、ひとりぼっちでなくなるぞ?」
「私に、早く嫁に行って欲しいの?」
「急かしておるわけではない。いつかはと言っておるのじゃ。嫁に行き子を成せ。我はおまえも、その子も、その孫も見守ってやろうほどにな」
生きている時間が違うのだと、知らしめる。みおに。そして自分に。
「……でも」
『でも』の先を言えばいいと思う。言ってくれるなと願う。どちらもどうしようもなく本心だ。
(聞いて、どうしようというのじゃ)
寂しさにつけ込み、人から引き離して、どうするつもりなのか。己は、人ではないのだ。
「さ、水を汲むのじゃろ?」
言葉の先を浚うように促せば、少女は素直に頷いた。
「うん。あ、そういえば」
「なんじゃ」
「呼べって言ったけど、名前も知らないのにどう呼ぶの?」
名前──真名とは弱みだ。真名を用いれば、時にその存在を消滅させることも出来る。だからこそ、妖同士は互いを呼ぶ時には真名を使わない。人でいうところの、あだ名で呼びあうのだ。
真名を教えるということは、二心がないことを示す特別なことだ。だからこそ、天帝やつがう者に差し出す。
けれど、少女は真名を知る意味など、知らなくていい。彼女は人として生きていくべき者だ。だから、差し出されたものの意味など、知らないまま生きていけばいいのだ。
「……璃卯」
「りう?」
少女の唇からこぼれる己が名に、心が震える。真名というのは体に、魂に響くものだ。こんなにも心が震えるのは、ただそのせいだ。それだけだ。言い聞かせる。
「そうじゃ。璃卯、という」
「それ……名前?」
「そうじゃ。もしも水に落ちたら」
「璃卯……璃卯、璃卯、……璃卯?」
呟くように微笑むように、幾度も繰り返すみおの声が、璃卯を誘う。触れて攫ってしまえばいいと、本能が囁く。
(浅ましいことじゃ……)
長く生きたところで、所詮人外だ。天帝と天帝の国に住まう神仙のように、清き心で多くに慈愛を注ぐ貴き者にはなれないのかもしれない。
それでも、目の前の少女には幸せな生を全うさせてやりたいと心から願う。
「聞いておるのか?」
「璃卯。うん、璃卯。璃卯……」
「連呼するでない」
「だって、嬉しいんだもん」
「よいから、汲むならとっとと汲め」
「ねぇ、声が届くのは水に入ってる時だけなの? 水に触ってれば声が届くの?」
「触っているだけでは駄目じゃ。体が半分以上浸かっていればよい」
「ふーん。だったらタライに水を溜めてそこに入ってもいいの?」
璃卯はぎょっとしながら少女を見た。よもや、行水でもしながら呼びかけるつもりだろうか。
「それは、無理?」
「む、無理じゃな。うむ、無理じゃ。だいたいそういうどうでもよい時の為に与えたのではないぞ? 川やら泉に落ちた時だけにしろ」
「うん、わかった。璃卯、ありがとう」
「……うむ」
「璃卯。璃卯……」
繰り返す少女の声が、切なく心に染み渡った。