コナン夢・降谷夢というかバーボン夢もどきというか……💦
ワンライの規定通りジャスト1時間で書いたけども、初書きのうえかなりいろいろゆるゆるふんわり設定ですw
我ながらツッコミどころ満載だからそのうち書き直すかもですが、いったん手を加えずにサイトに再録。
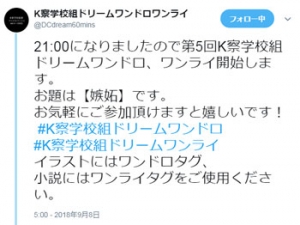
-------------------------------------
リボンタイを留める宝石の輝き。けれど、舌なめずりでもしそうな顔で向けられるねっとりとした視線の多くはそれを身につける男へと注がれる。
宝飾品のオークションとは名ばかりの人身売買。
組織が取り仕切る施設を使ってのそれを探りに来たはずの男が売られる側にまわったのは想定外のことではあったが、この場合はやむを得ないと言うべきか。
蝶を模る黒いレースのベネチアンマスクの下に秘められた素顔。それでも、覗く陽光に透ける海のような瞳、整った鼻筋にこれまでとは格段に上質の商品が現れたというのは誰の目にも明らかだった。
無粋な縄や鎖に戒められることもないままに木製のアンティークの椅子に腰掛け、口元には笑みまで湛えている。その余裕の表情を崩してみたいという嗜虐心をそそられるのか、それとも飾って眺めておきたい気持ちにさせるのか。人を金で買おうなどと考える者の思考回路など考えたくもないが、一段二段と価格が跳ね上がっていく。
「七千三百万。ありませんか?」
ここまで引き上げるところには漕ぎ着けたが相場の動きはいよいよ緩やかとなり、競売人の掛け声に対する会場の反応も鈍くなってきていた。ここらが潮時。これまで価格がつり上がろうとも声を上げていた参加者も手元のパドルを上げようか戸惑いが見られる。
この際落札されるのは吝かではないが、まだ早い。今少し、時間が欲しい。苛立ちを隠すように僅かばかり足下に視線を落とす。すると椅子の半歩後ろに控えていた主催者側の男の手が伸びてきた。
「おいおい、子猫ちゃん。そのお綺麗な顔をもっとちゃんと見せたらどうだ?」
ごつい指先が顔を上げさせようと、強引に顎をとった。おあつらえ向きのタイミングに内心ほくそ笑みながら、すかさずその手をはたき落とす。
「安い汚らわしい手で触らないで貰えますか。僕に触れていいのは……落札された方、ただひとりだ」
艶然と微笑み、そうでしょう? と同意を得るように会場を見渡してから長い脚をこれみよがしに組み替える。どこからともなくため息ともつかない声が響く会場は一瞬シンと静まり、再びいくつものパドルが上がりだした。
「八千。……八千二百万。……八千五百」
これでどうにか次へと順番がまわるのを留められるはず。そう思いながらゆるく息を吐き、もう一度落札者達が居並ぶ座席へと視線を走らせる。参加者は皆同じように仮面を被り、互いの素顔を晒さずにいる。落札したらすぐに上層階で購入品でお楽しみの輩ばかりだから、代理人が参加していることはないというのは事前情報で確認済みだった。
人を人とも思わぬ輩。反吐が出るような者たちだが、ここに居るのは多くの善良な国民の中に紛れ込むごく少数の悪人たちだ。
自分が守るべきものを再度胸の中で確認している傍で、落札を告げる木槌の音が会場に響いた。
その瞬間。会場が真っ暗闇に包まれる。これを待っていた。
常ならば落札者にスポットライトが当たるはずのところだというのに、突然の停電に会場の空気が大きく揺れる。
男は素早く身を翻し、舞台袖で控えた次の出品者の元へ音もなく忍び寄ると見張りを一撃で沈めた。
「ちょっ」
「しっ! 黙って」
まだ暗闇に目は慣れずとも、声で誰かはわかったのだろう。女はすぐに口を噤んだ。胸元の大きく開いたドレスはスリットも深く、太股どころか下着まで覗く。上着でもあれば着せかけたいところだったがあいにくそこまでの余裕はない。
荷物のように担ぎ上げれば、驚くほどに軽い肢体はなんなく肩の上に乗っかった。担がれて腹があたったのか小さく呻く気配もあったが、今はそれに構う余裕もない。
舞台から飛び降り、混乱の直中へと駆け込んで出口の扉の向こうへと滑り込む。
重厚な扉の向こうでは、わっと声が上がった。今頃会場内は明るく照らし出され、行き違いに突入した警察官たちの登場に蜂の巣を突いた騒ぎに陥っているはずだ。
「あちらに車が」
「後は頼んだ。……ああ、これも押収品だ」
彼女の長い髪を束ねた真珠の髪飾りを乱雑に外せば、解放された髪がばさりと肩にかかる。
「なっ、ちょっと」
「煩い。まだ黙っていろ」
自身の胸元を飾っていたブローチと合わせて風見に押しつけると、降谷は迷いのない足取りで駐車場を目指す。
用意された車はいつもの愛車ではないものの、こんな場所から逃走するならあれは避けるべきだ。部下の賢明な判断にささやかな称賛を送りながら、降谷は肩に担いだ荷物を助手席へと押し込み、すぐに運転席へと乗り込む。
シートベルトをするのもそこそこにアクセルを踏み込むと、ようやくそれで息がつける心地になった。
不満そうな恋人は、気の強い眼差しでこちらを精一杯睨み付けている。それでも先程担いでいた間に感じていた細い肢体の震えを思えば、灸は十分にすえられていることもわかっている。
「僕以外にその肌を晒したんだ。覚悟は出来ているだろうな?」
横目に窺えば、はくりと反論を紡ぎかけた唇は、むぅと何も言えずに閉じられた。
本当はすぐにでも庁舎へ向かわなくてはいけないところだ。とはいえ、彼女をセーフハウスに送り届けるくらいの時間はある。一番近いセーフハウスを思い描きながら、せめてその震えが収まるまでは傍にいてやれるだろうかと算段しながら、更にアクセルを踏み込んだ。